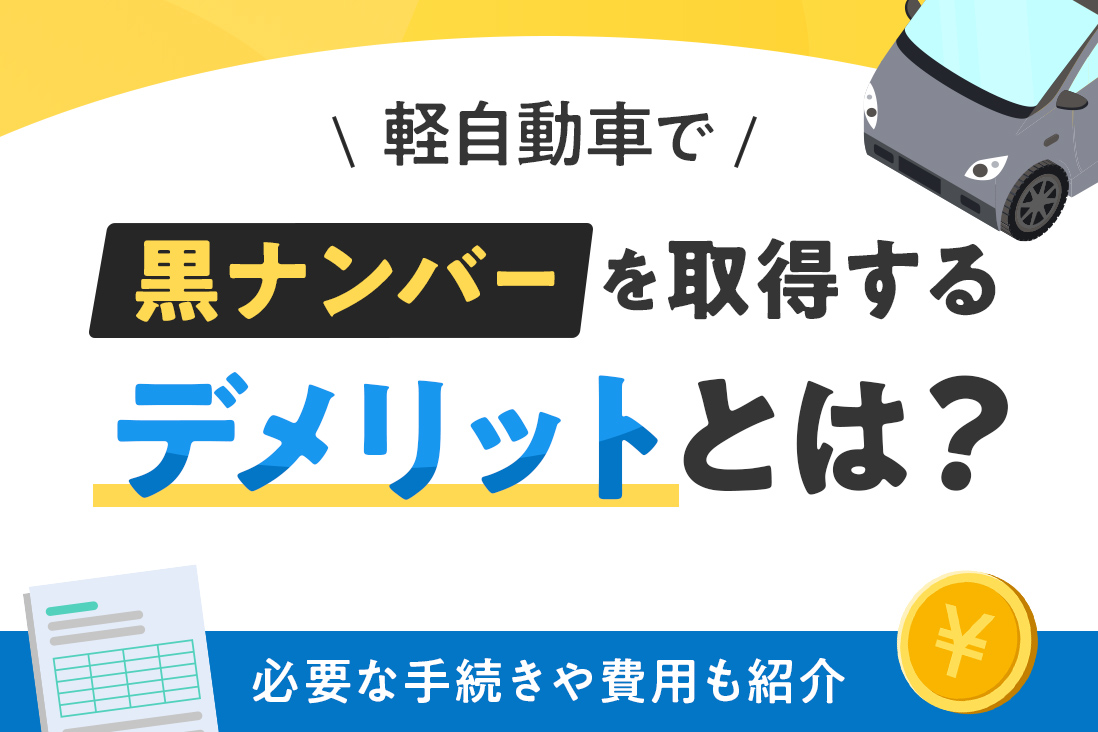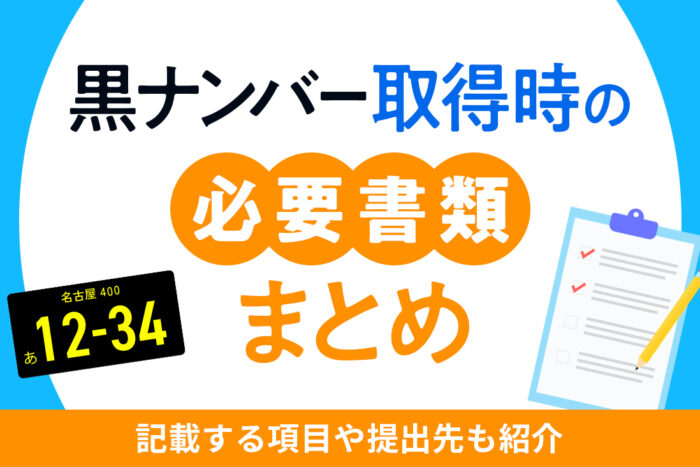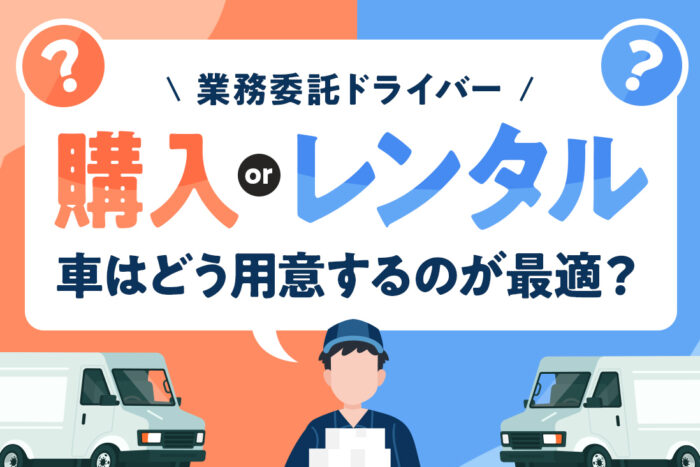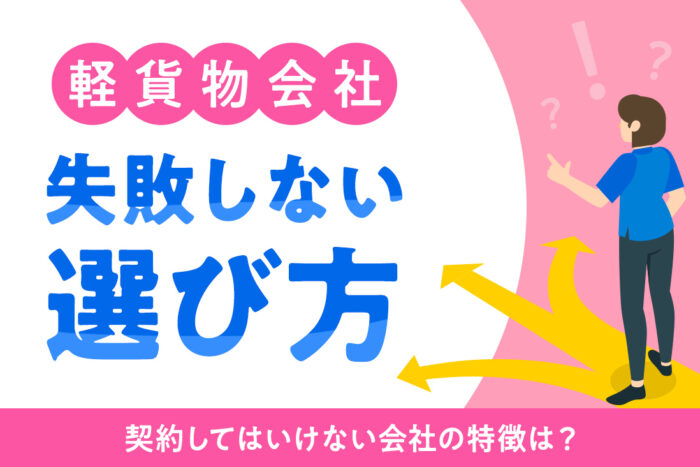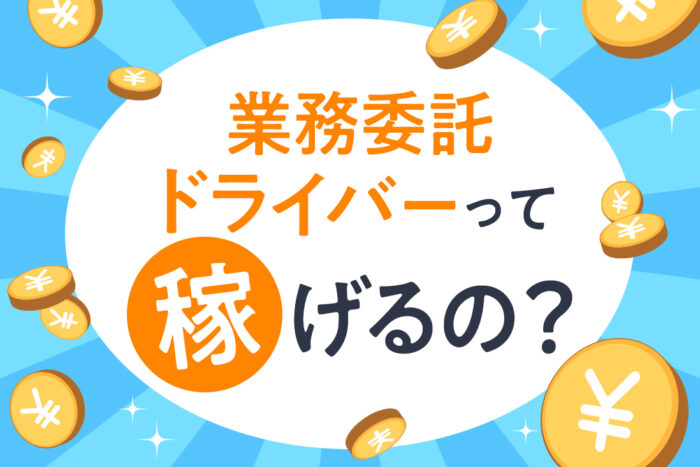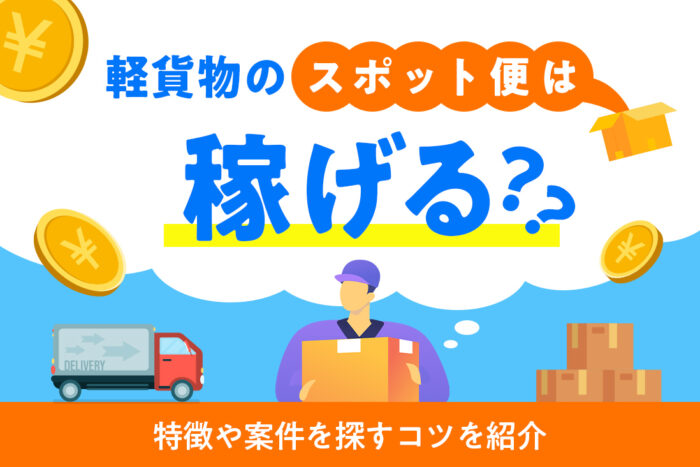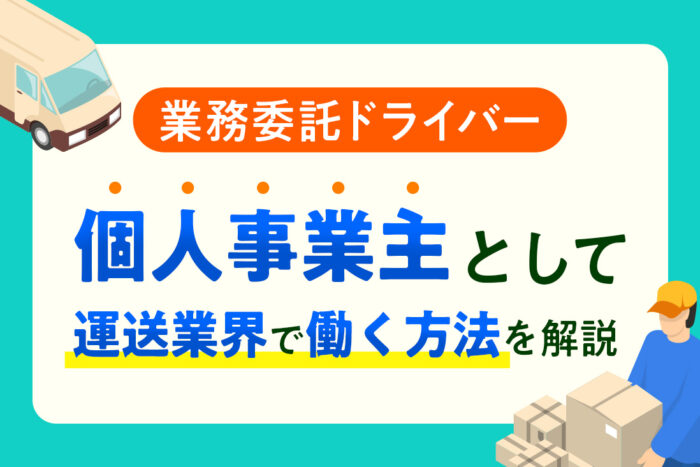軽自動車を使って軽貨物運送業に従事する場合には、黒ナンバーの取得が必須となります。自家用の軽自動車と黒ナンバー車では、用途はもちろん税金や車検期間などが異なるため、予めそれぞれの違いやメリット、デメリットを把握しておくことが望ましいです。
今回のコラムでは、黒ナンバーとは何かを改めて詳しく解説するとともに、軽自動車で黒ナンバーを取得するメリット、デメリットを紹介していきます。軽貨物ドライバーとしての稼働を見据え、黒ナンバーを取得しようとしている方はぜひご覧ください。
全国2,000人の業務委託ドライバーがギオンで活躍しています!
軽貨物配送・業務委託ドライバーの求人応募はギオンデリバリーサービスにお任せください。
・大手ECとのパートナーシップで豊富な案件数
・配送車両のリース可能
・働くエリア・時間は自由
未経験者からベテランまで、幅広くドライバーを募集中!ぜひお気軽にご応募ください!
全国に40以上の拠点を構え、年齢問わず2,000人ものドライバ―に案件を提供しているおすすめの軽貨物会社「ギオンデリバリーサービス」。ぜひ下記のリンクから採用サイトをチェックしてみてください。
本サイトでは、個人事業主として運送会社と直接契約を結ぶ業務委託ドライバ―の働き方も詳しく紹介しています。おすすめの軽貨物会社「ギオンデリバリーサービス」の特徴もまとめていますので、ぜひ下記のリンクからご覧ください。
目次
黒ナンバーとは
| 普通自動車 | 自家用 | 白ナンバー | 白地に緑文字 |
|---|---|---|---|
| 事業用 | 緑ナンバー | 緑地に白文字 | |
| 軽自動車 | 自家用 | 黄ナンバー | 黄色地に黒文字 |
| 事業用 | 黒ナンバー | 黒地に黄色文字 |
車のナンバープレートは上記の4種類に大別でき、車両のサイズや用途に応じた色が割り当てられています。
自家用車に取り付けられる白ナンバーや黄色ナンバーは、普段から見慣れていて身近に感じる方がほとんどではないでしょうか。緑ナンバーが採用されるのは、事業用の普通自動車。貨物や旅客などを運ぶバスやトラック、タクシーなどが該当します。
今回詳しくご紹介する黒ナンバーは、事業用の軽自動車に取り付けられるナンバープレートです。
黒ナンバーのない軽貨物車両で運送業務を行うことは法律上できません。軽貨物ドライバーにとって、黒ナンバーの取得は事業を始める上で避けては通れない手続きだと言えます。
黒ナンバーと緑ナンバーの違い
黒ナンバーと緑ナンバーはともに営業用のナンバープレート(営業ナンバー)であるため、よく混同されがちです。これら二つのナンバーの主な違いは、対応している事業内容と使用車両にあります。
緑ナンバーは貨物自動車運送事業や旅客自動車運送事業に必要とされ、タクシー、バス、トラックや大型車両などに取り付けられます。一方、黒ナンバーが必要なのは貨物軽自動車運送業で、軽自動車に取り付けられます。
また、取得要件も大きな違いの一つです。黒ナンバーは「届出制」のナンバープレートです。個人・法人を問わず、運輸支局に所定の手続きを届け出るだけで取得できます。これに対し、緑ナンバーは取得条件が非常に厳しく、主に以下のような条件が定められています。
- 5台以上の営業用車両を確保する
- 事業所が適切な営業立地である(法令に準じている・ある程度の規模)
- 運行管理者を有している
黒ナンバーと白ナンバーの違い
多くの方にとって最も馴染み深い一般的なナンバープレートである白ナンバー。通常の車両登録を済ませるだけで取得することが可能です。自家用車をはじめ、営業目的以外で使用されるすべての車両に取り付けられます。
配送ドライバーは、その稼働形態に関わらず、白ナンバーの車両を用いて運送業務を実施することはできません。
【軽自動車】黒ナンバーのメリット

軽貨物ドライバーが軽自動車で黒ナンバーを取得するメリットについて、自家用つまり黄色ナンバーの軽自動車と比較しながら紹介していきます。
すぐに独立・開業できる
黒ナンバーを取得するのに必要な初期費用は3,000円程度であり、書類の記入や手続きは基本的に1日で完了させることが可能です。普通自動車免許を保持していれば、軽貨物ドライバーとしてすぐに稼働を始められます。
税金が安く済む
軽自動車の所有者に支払い義務が生じる税金は以下の通りです。
| 黄色ナンバー車(自家用) | 黒ナンバー車(事業用) | |
|---|---|---|
| 自動車税 | 5,000円 | 3,800円 |
| 自動車重量税 | 6,600円 | 5,200円 |
※2025年2月時点
金額は基本的に一律ですが、自動車税、自動車重量税ともに軽貨物ドライバーが使用する黒ナンバー車の方が安くなっています。
普段使いもできる
個人事業主の軽貨物ドライバーとして稼働する場合、自家用車と配送車をそれぞれ確保しようと思うと、2台分の駐車スペースを設けたり維持費を支払ったりする必要があります。
黒ナンバー車は普段使いが可能であるため、プライベートと配送業務の両方で使用すれば税金や固定費を安く抑えることが可能です。ただし、条件によって乗車定員や最大積載量が変わってくるといったポイントには留意しなければなりません。
黒ナンバー車を普段使いする際の注意点については、下記の記事でさらに詳しく解説しています。興味がある方は、ぜひ合わせてチェックしてみてください。
軽自動車で黒ナンバーを取得するデメリット

軽自動車で黒ナンバーを取得すると上記のようなメリットがある一方で、以下のようなデメリットも存在します。
任意保険料が高くなる
黒ナンバー車の任意保険料は、黄色ナンバー車よりも高くなることがほとんど。軽貨物運送事業に使用する以上、自家用車に比べて走行距離や使用頻度が多くなり、その分事故のリスクも高いとみなされるためです。
自家用車の任意保険でつけられるような特約も基本的にはなく、保険会社によっては黄色ナンバー車の2倍以上の保険料を支払わなければならないことも珍しくありません。
任意保険の等級の引き継ぎに手間がかかる
黒ナンバー車の割高な任意保険料を抑える方法の1つとして、自家用車で加入していた任意保険の等級を引き継ぐことが挙げられます。等級が高い方であれば、月々の保険料を数万円近く削減できるケースもあります。
ただし、契約者や保険会社が同一であるといった条件を満たさなければならず、手続きもかなり煩雑です。黒ナンバー車に任意保険の等級を引き継ぐ手順や条件については、下記の記事で詳しくまとめていますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。
初回の車検期間が短い
軽自動車の車検の有効期間は以下の通り。
| 黄色ナンバー車(自家用) | 黒ナンバー車(事業用) | |
|---|---|---|
| 初回(新車時) | 3年 | 2年 |
| 2回目以降 | 2年 | 2年 |
自家用、事業用に限らず2回目以降は2年ごとに車検を行いますが、黒ナンバー車の初回の車検期間は自家用車に比べて1年短く、損だと感じる方もいるかもしれません。
軽自動車で黒ナンバーを取得する条件
軽自動車で黒ナンバーを取得する際には、以下の条件を満たしている必要があります。
- 1台以上の軽貨物車を保有している
- 営業所・休憩施設・車庫を保有している
- 運送約款
- 運行管理能力がある
- 損害賠償能力がある
配送車だけでなく、営業所や車庫、休憩所などを用意しなければなりません。個人事業主の場合は自宅を営業所や休憩施設として登録できるため、場所を確保できるかどうかといった心配は不要です。
運送約款とは、貨物自動車運送の取り引きに関する基本的な事項が定められた文書のことです。自身で作成することもできますが、国土交通省のホームページに掲載されているものをダウンロードするのがスムーズでしょう。
運行管理能力を証明するためには、業務前後の点呼や過積載の防止などを管理する担当者を設ける必要がありますが、個人事業主の場合は自分自身を登録すれば問題ありません。損害賠償能力については、自賠責保険や任意保険に加入することで証明が可能です。
軽自動車で黒ナンバーを取得する際の手続き
黒ナンバーを取得する際には、以下のような流れで手続きを行います。
- 必要書類を準備する
- 運輸支局に必要書類を提出する
- 軽自動車検査協会に必要書類・黄色のナンバープレートを提出する
- 黒ナンバーを取得する
書類の提出先となる運輸支局と軽自動車検査協会は隣り合っている場合が多いですが、場所によっては離れており、移動に時間がかかることもあります。
それぞれの機関に提出する書類は以下の通り。
<運輸支局>
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書
- 運賃料金表
- 事業用自動車等連絡書
- 運賃料設定届出書
- 車検証
<軽貨物検査協会>
- 申請依頼書
- 事業用自動車等連絡書
- 車検証(原本)
- ナンバープレート
各書類に記載する項目や記入例などについて詳しく知りたい方は、下記の記事も合わせてチェックしてみてください。
【軽自動車】黒ナンバーの取得前後にかかる費用

ここからは、軽自動車で黒ナンバーを取得する際に発生する費用について解説します。
取得前
- ナンバープレートの取得:1,500~2,000円
- 住民票・印鑑証明書の発行:約500円
- 車庫証明書の発行:約500円
黒ナンバーを取得する際には、上記のような費用が発生します。合計すると3,000円程度。一連の手続きは代行サービスに依頼することもできますが、2~5万円程かかることが一般的であり、自身で済ませる方がずっとお得です。
なお、ナンバープレートの取得費用は地域によって異なるため、一度最寄りの運輸支局に確認してみてください。
取得後
黒ナンバーを取得した車両には、以下のような維持費がかかってきます。
- ガソリン代
- メンテナンス費用
- 自賠責保険料
- 任意保険料
- 車検代
自賠責保険料や車検代などは、自家用車の場合とそれほど変わりありません。
しかし、業務に伴って走行距離が長くなる分、ガソリン代はどうしても高くなります。部品の消耗も激しくなるため、エンジンオイル、バッテリー、タイヤ、ブレーキなどのメンテナンス費用もかさみやすくなります。
任意保険料も割高であることから、黒ナンバーの維持費は自家用車に比べて高くなるケースが一般的です。
ただし、個人で軽貨物ドライバーとして稼働する場合、こうした費用を経費として計上することができます。節税効果を最大限得るため、収支をきちんと帳簿に記録しておく習慣をつけておけると良いでしょう。
黒ナンバーを取得した軽自動車は普段使いできる
事業用として登録される黒ナンバーの車両ですが、プライベートでの使用も可能です。ただし、日常使いをする際には、以下の点に注意が必要です。
- リース契約で入手した車両では普段使いが制限されるケースもある
- 基本的に3人以上での乗車ができない
- 普段使いでのガソリン代は経費計上できない
契約したリース会社によっては、普段使いを制限していたり、契約期間中の走行距離が限られている場合があるので要注意です。
本来、軽自動車は4人乗りが可能ですが、貨物の配送を主目的としている黒ナンバーの軽自動車は、後部シートを収納して荷室として利用するため2人乗りであることが一般的です。ご家族が多い場合、全員が同乗して移動する用途には適していません。
また、プライベートで走行した分のガソリンは経費として計上できません。私的に使った分を申告するとペナルティが課される可能性も考えられます。事業用の走行とプライベートの走行を区別して管理することも求められます。
軽自動車での黒ナンバー取得はデメリットだけではない
軽自動車で黒ナンバーを取得すると任意保険料が高くなる、初回の車検期間が短いといったデメリットがあります。しかし、軽貨物ドライバーとして稼ぎたいと考える方にとっては、すぐに手続きを済ませられる、税金を安く抑えられるなどメリットも大きいです。
軽貨物ドライバーは、今回ご紹介した方法で黒ナンバーを取得して開業届を提出すれば個人事業主として開業することができます。頑張り次第で高収入を目指せることは大きな魅力の1つです。興味のある方は、ぜひ一度自身での開業を検討してみてはいかがでしょうか。
この記事の執筆者

軽カモツネット編集部
軽カモツネットは株式会社ギオンデリバリーサービスが運営する、軽貨物ドライバー向けの情報発信メディアです。運営元のギオンデリバリーサービスは2013年の設立以来、神奈川県相模原市を中心に業務委託ドライバーの開業支援や宅配サービスの運営など多岐にわたるサポートを行ってきました。拠点数は全国40カ所以上、約2,000名のドライバーが、日々安全で効率的な配送をご提供しています。軽カモツネットでは、軽貨物ドライバーの皆様のニーズに応え信頼される情報を発信してまいります。