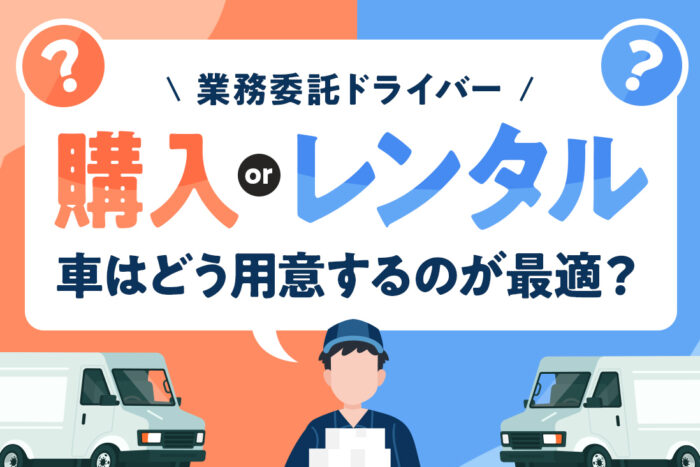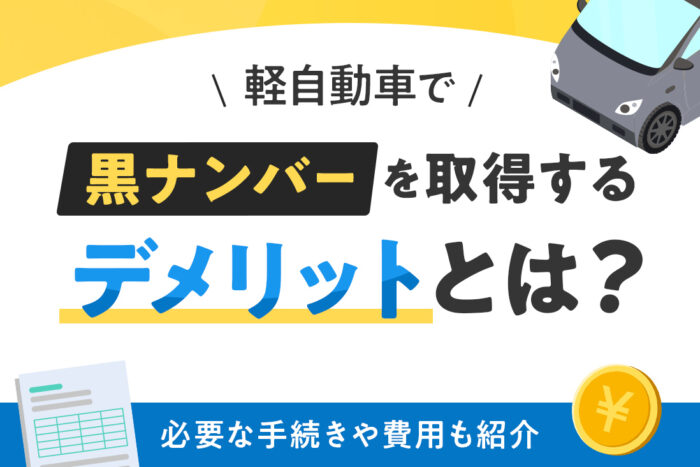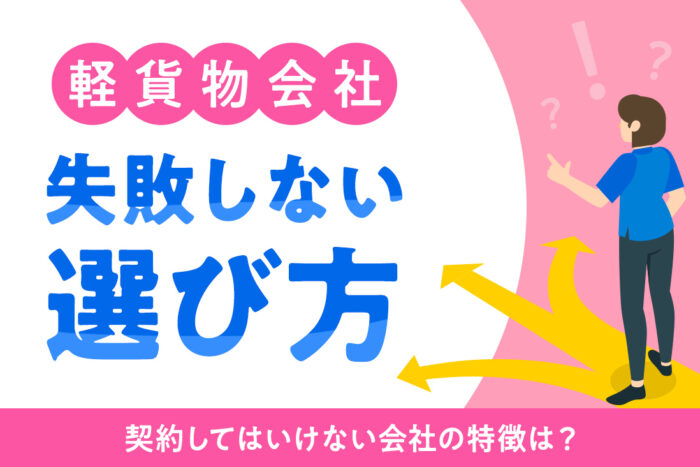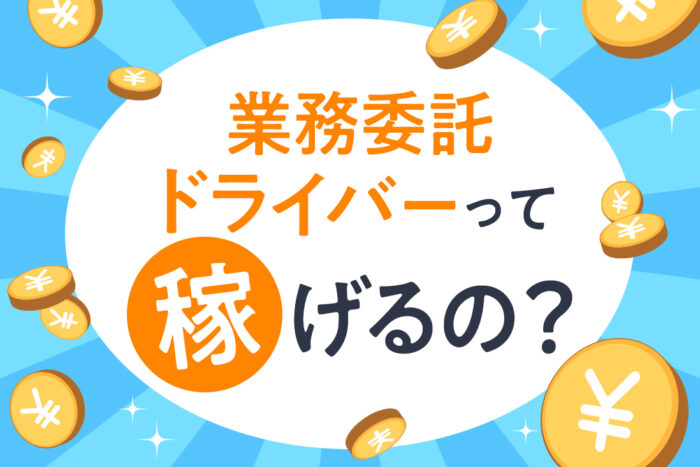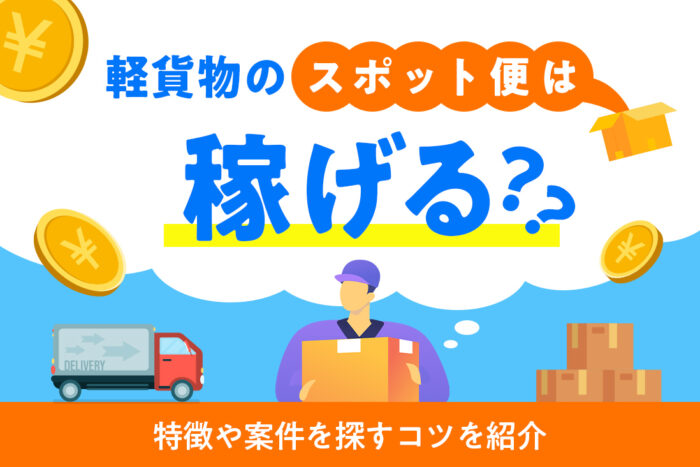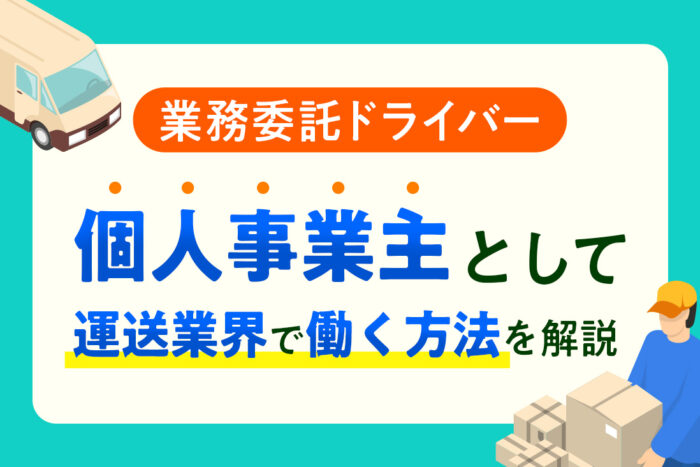環境意識の高まりや燃料費の高騰を背景に、軽貨物の現場でも電気自動車(EV)への関心が高まっています。電気自動車は走行コストを大幅に削減できるだけでなく、静粛性や環境負荷の低減など、配送業務に適した多くのメリットを持っています。
ここ数年、各メーカーから軽バンEVが相次いで登場し、国や自治体による補助金制度も充実してきました。軽貨物ドライバーにとって、電気自動車への切り替えは単に環境に配慮できるだけではなく、業務の効率を高められる重要な選択肢となっています。
本記事では、軽貨物ドライバーが知っておきたい電気自動車の基礎知識から導入メリット、主要車種の比較まで網羅的に解説します。
目次
そもそも電気自動車とは

電気自動車(EV)は、バッテリーに蓄えた電力をモーターで駆動する、走行中に排ガスを出さない自動車です。従来のガソリン車とは異なり充電した電力を使って走行するため、CO2排出量の削減に大きく貢献します。
近年は環境規制の強化や脱炭素社会への移行を背景に、国や自治体が電気自動車の普及を積極的に支援しています。充電インフラも急速に整備が進んでおり、2025年9月時点で全国の充電スタンド数は26,005拠点に達しました。
軽貨物業界においても、大手運送会社を中心に軽バンEVの導入が進んでいます。特に都市部でのラストワンマイル配送では、静粛性や環境性能の高さが評価され、配送車両のEV化が加速しています。
【軽バン】電気自動車(EV)とガソリン車の違い
電気自動車とガソリン車の違いを下表にまとめました。
| 電気自動車 | ガソリン車 | |
|---|---|---|
| 動力源 | バッテリー・モーター | ガソリンエンジン |
| 燃料費 ※3,000km走行時 | 約1~1.5万円 | 約3~4.5万円 |
| メンテナンス | 低コスト | 高コスト |
| 走行音 | 静か | エンジン音あり |
| 排出ガス | なし | CO2 |
| 航続距離 | 150~250km | 400~600km |
最も大きな違いとして挙げられるのが、動力源です。ガソリン車は内燃機関で燃料を燃やして動力を得るのに対し、電気自動車はバッテリーに蓄えた電力をモーターで駆動させます。
そのため、電気自動車にはエンジン音がなく、走行時の静粛性が極めて高いです。早朝や深夜の住宅街での配送業務において、騒音を気にせず作業できる点は大きなメリットだと言えるでしょう。
コスト面でも優位性があります。エンジンオイルのような定期交換が必要な部品が少なく、長期的な整備・保守費用を抑えやすいです。さらに、燃料価格変動の影響を受けにくく、夜間電力など料金の安い時間帯を活用して充電すれば、走行コストを安定的に低減できます。
軽貨物ドライバーが電気自動車(EV)を導入するメリット

電気自動車の導入は、軽貨物ドライバーの業務効率と収益性を大きく向上させてくれる可能性があります。ここでは、電気自動車ならではの4つの主要なメリットを詳しく解説します。
ランニングコストの大幅な削減
軽貨物ドライバーにとって、燃料費は毎月の経費の中でもかなり大きな割合を占めるコストですが、ガソリン車から電気自動車に切り替えることで大幅な削減が期待できます。
例えば、月間3,000km走行する場合、ガソリン車では約4万円の燃料費がかかるのに対し、軽バンEVでは電気代が約1万円程度に収まります。これだけで、月々3万円以上のコスト削減が実現できる計算です。
事業所や自宅に充電設備を設置し、夜間電力など料金の安い時間帯を活用すれば、電力コストをさらに抑えることができます。年間で換算すると30万円以上の経費削減も可能です。
電気自動車は車両価格が高いのが懸念ですが、その出費を十分に補えるだけの経費削減効果が期待できます。
メンテナンス費用の低減
ガソリン車にはエンジンオイルの交換といった定期的なメンテナンスが欠かせません。こまめな部品交換や点検には、決して少なくない費用と時間がかかります。
一方、軽バンEVは電気モーターで走行するため、ガソリン車では必須だったエンジン周りの定期メンテナンスの手間が大幅に削減されます。オイル関連の交換が一切不要になるだけでも、年間数万円の節約に繋がるでしょう。
電気自動車は減速時に発生する運動エネルギーを電気エネルギーに変換してバッテリーに回収・再利用する回生ブレーキを積極的に利用します。そのため、ブレーキパッドの摩耗が少なく長持ちする傾向があり、長期的なランニングコストも削減することが可能です。
静粛性による業務環境の向上
ガソリン車ではエンジン音が大きい車種も多いですが、電気自動車は電気モーターで駆動するため走行中の騒音が小さく、振動も少ないのが特徴です。
早朝や深夜の住宅街での配送でも騒音を過度に気にせず作業でき、周辺環境への配慮やクレーム抑制の面でも大きな強みとなります。
スムーズな加速性能
電気モーターは停止状態から瞬時に最大トルク(回転力)を発生できるという特性を持っています。これにより、電気自動車では発進から非常にスムーズかつ力強い加速を実現することが可能です。
都市部の配送業務では特に、信号待ちからの発進や幹線道路への合流など、頻繁なストップ&ゴーが求められます。電気自動車のスムーズな走りは、ドライバーのストレスを大きく軽減してくれるでしょう。
主要な軽バンEVの車種を比較
現在市場で入手可能な主要な軽貨物EVとして、日産クリッパーEV、ホンダN-VAN e:、三菱 MINICAB EVの3車種が挙げられます。それぞれの特徴を比較してみましょう。
| 航続距離 | バッテリー容量 | 車両価格(税込) | 荷室内寸法 | |
|---|---|---|---|---|
| 日産 クリッパーEV | 180km | 20kWh | 2,865,500円~ | 1,830×1,370×1,230mm |
| 三菱 MINICAB EV | 180km | 20kWh | 2,431,000円~ | 1,830×1,375×1,230mm |
| ホンダ N-VAN e: | 245km | 約29.6kWh | 2,699,400円~2,919,400円 | 1,480×1,390×1,365mm |
日産クリッパーEV・三菱 MINICAB EV
日産「クリッパーEV」と三菱「MINICAB EV」はOEM関係にあり、主なスペックはほぼ共通です。航続距離は約180kmで、1回充電すれば宅配業務で1日走行するのに十分な余裕を確保できるでしょう。
日産「クリッパーEV」のバッテリーは「8年160,000km」が保証されており高寿命。後輪駆動方式を採用しているため坂道でも力強く、荷物を積んだ状態でもスムーズな加速を実現します。
最大積載量はガソリン車同様に350kgを確保しており、コンパネの平積みも可能です。なお、価格面では三菱ミニキャブEVの方がやや手頃な設定となっています。
ホンダ N-VAN e:
ホンダ「N-VAN e:」は、航続距離が245kmと長めなのが特徴です。その分バッテリー容量も大きく、長距離配送が多い事業者にとって嬉しい選択肢となります。
加えて、充電性能も優秀です。普通充電は6kWに対応しており約4.5時間で満充電、急速充電では30分で電池容量の80%を充電できる高速仕様。航続距離の長さやホンダの先進安全装備といった付加価値を考慮すると、総合的な性能バランスに優れた車種だと言えます。
電気自動車(EV)導入時に知っておくべき注意点

電気自動車の導入は軽貨物ドライバーに多くのメリットをもたらしますが、最大限に効果を引き出すためには、以下の注意点を事前に理解しておく必要があります。
航続距離と配送ルートの適合性
車種によって異なりますが、軽バンEVの航続距離は150~250km程度です。ただ、エアコンの使用などを考慮すると、実質的に20~30%程度短くなる可能性があります。
電気自動車はガソリン車に比べて航続距離が短いため、日々の配送ルートや走行距離を正確に把握し、必要距離を満たすモデルを選ぶことが重要です。
フルタイムで稼働する宅配ドライバーの1日あたりの走行距離は平均50km程度とされており、多くのケースでは1回の充電で十分カバーできます。しかし、長距離配送の案件が多いドライバーは1日あたりの走行距離がぐっと増えるため、注意しなければなりません。
充電スポットの位置や空き状況を事前に確認する習慣をつけておきましょう。
寒冷地での性能低下
寒冷時は電気自動車のバッテリー性能が低下しやすく、また暖房の使用により電力消費が増大します。
近年の軽バンEVはバッテリー温度管理機能を備えており、冬場の性能低下を抑制する工夫が施されていますが、念のため航続距離を3〜4割程度短く想定しておくと安心です。
また、充電中に暖房でキャビンを温めておくと、走行中の電力消費を減らすことができます。
バッテリーの寿命
電気自動車のバッテリー寿命は、充放電の回数や使用環境に大きく影響されます。一般的に、電気自動車のリチウムイオンバッテリーは8~10年、または15万km程度の走行で劣化が目立ち始め、交換を検討する目安とされています。
多くのメーカーでは、一定の年数または走行距離までの容量保証を設けており、規定の残存容量(%)を下回った場合は無償修理・交換の対象となります。適用条件は車種ごとに異なるため、購入前・運用中に保証内容を確認しておくと安心です。
なお、バッテリーの寿命を延ばすためには、以下のような対策が有効だとされています。
- 急速充電の多用を避ける
- 日常利用は80~90%で充電停止し、満充電を常態化しない
- 高温・極寒環境の長時間放置を避ける
電気自動車(EV)で持続可能な軽貨物配送業務を
電気自動車は環境負荷の低減だけでなく、ランニングコストの大幅削減や業務効率の向上など、軽貨物ドライバーにとって実質的なメリットをもたらしてくれます。
航続距離や充電インフラといった課題はありますが、都市部や近郊での定期配送であれば、軽バンEVでも十分実用は可能です。
軽貨物ドライバーとして長期的に活動することを見据えている方は、電気自動車への切り替えを検討してみてはいかがでしょうか。本記事で紹介した情報を参考に、自分の業務スタイルに合った最適な車両選びを進めてみてください。
この記事の執筆者

軽カモツネット編集部
軽カモツネットは株式会社ギオンデリバリーサービスが運営する、軽貨物ドライバー向けの情報発信メディアです。運営元のギオンデリバリーサービスは2013年の設立以来、神奈川県相模原市を中心に業務委託ドライバーの開業支援や宅配サービスの運営など多岐にわたるサポートを行ってきました。拠点数は全国40カ所以上、約2,000名のドライバーが、日々安全で効率的な配送をご提供しています。軽カモツネットでは、軽貨物ドライバーの皆様のニーズに応え信頼される情報を発信してまいります。