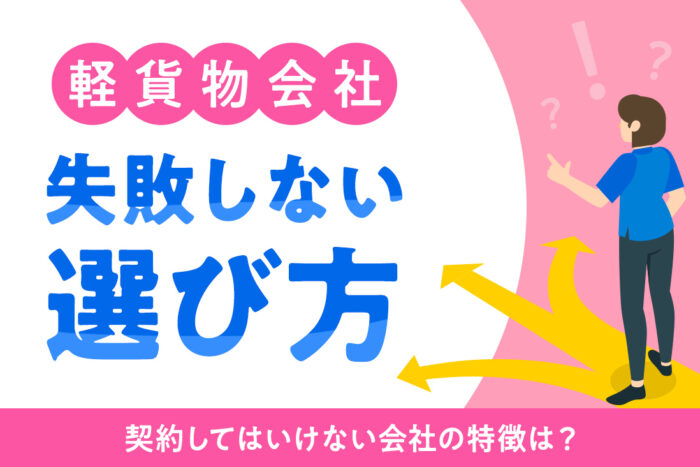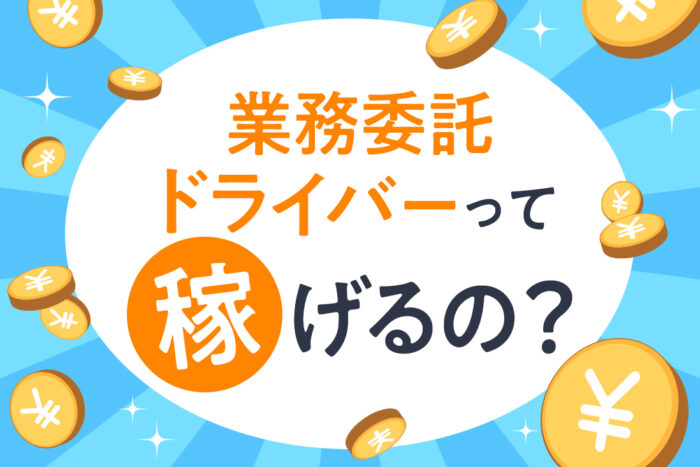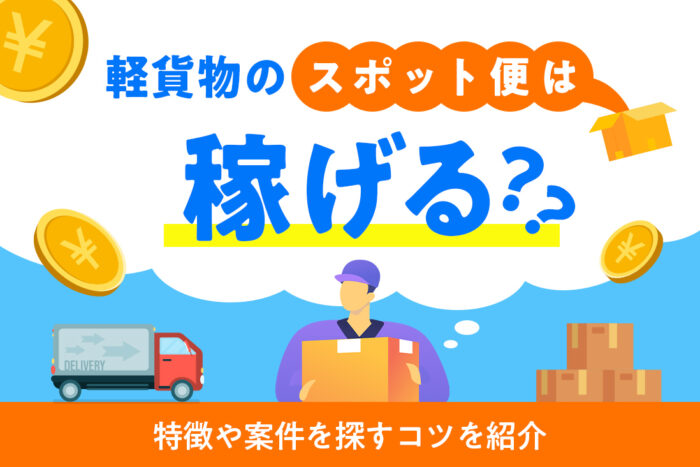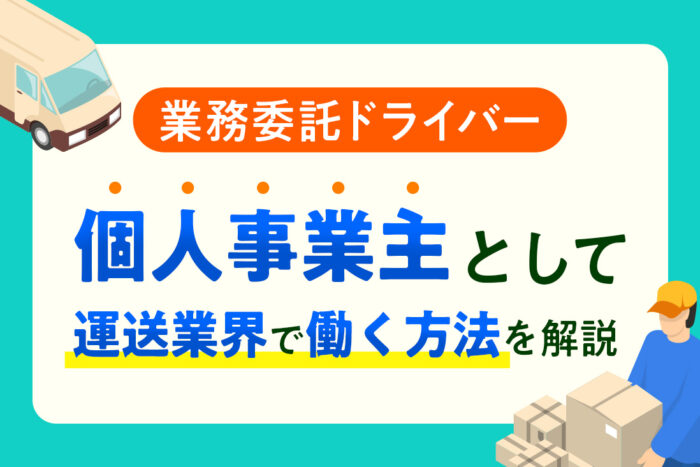オンラインショッピングの普及に伴い、宅配便の取扱量は増加を続けています。その一方で、不在による再配達も多く発生し、ドライバーの負担や人手不足、CO₂排出量の増加など深刻な問題を引き起こしています。こうした背景から再配達の有料化が検討されていますが、具体的な実施時期はまだ決まっていません。
本記事では、再配達の有料化が検討される理由や現在の状況を整理し、利用者ができる再配達削減の工夫についても詳しく解説します。
再配達の有料化はいつから始まる?

2025年10月時点で、再配達の有料化がいつ導入されるのかは決まっていません。「働き方改革関連法」の運用が始まる2024年から実施されるのではと予測されていましたが、ヤマト運輸や佐川急便など大手各社から正式な告知はなく、開始時期は依然として不透明です。
再配達の有料化が進まない要因としては、顧客の不満や利用者離れへの懸念、さらに業界全体で共通のルールを整える難しさがあるとされています。一方、議論自体は継続しており、今後具体的な実施時期が公表される可能性も高いです。
宅配便を利用する側にとっても、再配達制度のあり方が変わる可能性があるため、最新情報を把握し備えておくことが重要です。
なぜ再配達の有料化が検討されているのか?

近年、再配達をめぐる課題は、単に宅配業者だけの問題にとどまらず、社会全体に関わるテーマとして注目されています。
ここでは、再配達の有料化が検討されている主な理由を3つご紹介します。
物流業界を揺るがす「2024年問題」
物流業界で注目される「2024年問題」とは、「働き方改革関連法」によりトラックドライバーの年間時間外労働が960時間に制限されたことで生じている課題です。
働き方改革関連法の施行には、長時間労働を是正する効果が期待される一方で、輸送力の減少や人手不足の深刻化を招く恐れも指摘されています。
こうした状況への対応策の一つとして再配達の有料化が議論されており、持続可能な物流を実現するための重要なテーマとなっているのです。
ドライバーの負担増加
EC市場の成長やインターネットの普及により、消費者が手軽にオンラインで買い物を楽しむようになった結果、宅配便の取扱量は増加を続けています。国土交通省の統計によると、宅急便の取扱個数は令和2年度の48.4億個から令和5年度には50.7億個へと拡大しました。荷物量の増加に比例してドライバーの業務負担も大きくなり、稼働環境の改善が求められています。
再配達率は直近ではやや低下傾向にあるものの、令和2年度と比べると依然高水準で推移しています。そのため、荷物を効率的に届ける仕組みづくりは、物流業界全体にとって避けられない課題といえるでしょう。
※参考
報道発表資料:令和5年度 宅配便・メール便取扱実績について – 国土交通省
報道発表資料:令和7年4月の宅配便の再配達率は約8.4% – 国土交通省
CO2排出量の増加と環境への影響
再配達の増加は、ドライバーの負担や人件費の問題にとどまらず、環境にも大きな影響を及ぼしています。荷物を届けるために同じ場所へ何度も足を運ぶとトラックの走行距離が延び、燃料消費が増えることで、CO2の排出量も拡大してしまいます。
環境省の試算では、再配達によって排出されるCO2は年間でおよそ42万トンに達しており、自家用車数十万台分に相当するとされています。こうした状況を改善するため、再配達を有料化して無駄な配送回数を減らし、環境負荷を軽減しようという議論が進められています。
再配達の有料化が実現しない理由とは?

再配達有料化の実現に向けては、さまざまな課題が存在します。ここでは、再配達の有料化が実現しない主な理由を見ていきましょう。
顧客満足度の低下
顧客満足度への影響は、再配達の有料化が進まない理由のひとつとされています。これまで無料で利用できた再配達に料金がかかるようになると、送料と合わせた費用負担はより重くなります。
さらに、「宅配便の到着に合わせて在宅しなければならない」という状況は、多くの利用者にとってストレスとなりかねません。
とりわけ通販を頻繁に利用する人や在宅時間が限られている人にとって、再配達の有料化は利便性を損なう要因として受け止められる可能性があります。
業界全体でのルール作りの必要性
再配達を有料化する際には、業者ごとに料金やサービス内容が異なると利用者が不満を抱き、よりコストパフォーマンスの良い業者に依頼が集中する恐れがあります。そのため、ヤマト運輸や佐川急便といった大手から中小の運送会社まで、業界全体で統一した仕組みを整えることが重要です。
しかし、各社の事情を調整して合意に至るには時間がかかり、さらに政府や関連機関のガイドラインも考慮する必要があるため、議論は複雑化することが予想されています。
配達トラブルのリスク
近年、配達員がインターホンを鳴らさず不在票を入れるという行為が報告されています。ヤマト運輸や佐川急便、日本郵便といった大手事業者は「必ずインターホンを鳴らすこと」をルール化していますが、個々の配達員のモラルに関わる問題であり、必ずしも可能性がゼロとは言い切れません。
再配達が有料化された場合、在宅していたにもかかわらず不在扱いにされてしまうと、利用者に不利益が生じ、業者とのトラブルにつながる懸念があります。
再配達を少なくするにはどうすればいい?

再配達を減らすためには、利用者側が受け取り方法を工夫することが大切です。
主な方法として以下の3つが挙げられます。
宅配ボックスを利用する
宅配ボックスの活用は、再配達を減らす有効な手段のひとつです。玄関先などに設置しておけば不在時でも安全に荷物を受け取れるため、利用者は配達時間に縛られず快適な生活を送れます。運送業者にとっても一度の配達で荷物を届けられるため効率が向上し、負担軽減につながるでしょう。
そのため、受取人と配送側の双方にメリットをもたらす仕組みとして注目されています。
コンビニや宅配ロッカーを受け取り先に指定する
賃貸の集合住宅など宅配ボックスを設置できない場合は、コンビニや宅配ロッカーを受け取り先に指定する方法もおすすめです。24時間利用できる場所も多く、忙しい人でも時間を気にせず荷物を受け取ることができます。
自宅の近くや通勤経路上の施設を選べば、帰宅途中に立ち寄って効率よく荷物を受け取ることが可能。セキュリティ面にもしっかり配慮がなされているため安心感も高く、宅配ボックスがない環境でも気軽に荷物を受け取れる点が大きな魅力といえるでしょう。
配達通知や日時変更サービスを活用する
配達状況のお知らせサービスや日時変更サービスの活用も、再配達の削減に役立ちます。荷物の到着予定をメールやアプリで通知してくれるため、利用者はあらかじめスケジュールを把握でき、都合に合わせて受け取り方法を調整できます。
ヤマト運輸では公式アプリやLINE通知を通じて、受け取り日時や場所を簡単に変更できる仕組みが整っています。佐川急便や日本郵便などでも同様のサービスが導入されており、スマートフォンから手軽に操作が可能です。
急な予定変更にも柔軟に対応できるため、再配達を減らすだけでなく、利便性向上にもつながります。
再配達の有料化に備えてできる工夫を知っておこう
再配達の有料化は、ドライバーの負担軽減や環境問題への対策として検討が継続されていますが、実施時期は未定であり、顧客満足度や業界全体の調整といった課題も残されています。
議論の行方を見守りつつ、利用者自身が宅配ボックスや宅配ロッカー、コンビニ受け取り、日時変更サービスなどを活用することも重要です。一人ひとりが問題意識を持つことで、再配達の削減に貢献することができます。
この記事の執筆者

軽カモツネット編集部
軽カモツネットは株式会社ギオンデリバリーサービスが運営する、軽貨物ドライバー向けの情報発信メディアです。運営元のギオンデリバリーサービスは2013年の設立以来、神奈川県相模原市を中心に業務委託ドライバーの開業支援や宅配サービスの運営など多岐にわたるサポートを行ってきました。拠点数は全国40カ所以上、約2,000名のドライバーが、日々安全で効率的な配送をご提供しています。軽カモツネットでは、軽貨物ドライバーの皆様のニーズに応え信頼される情報を発信してまいります。