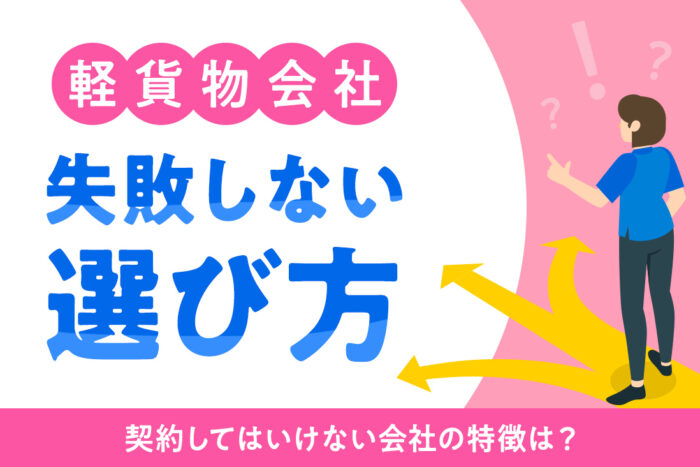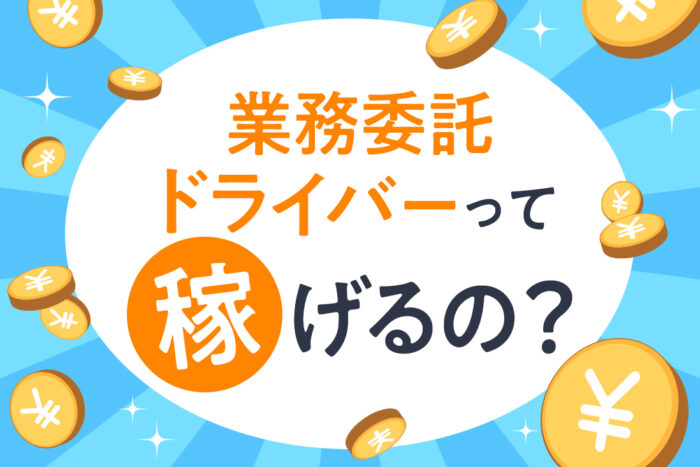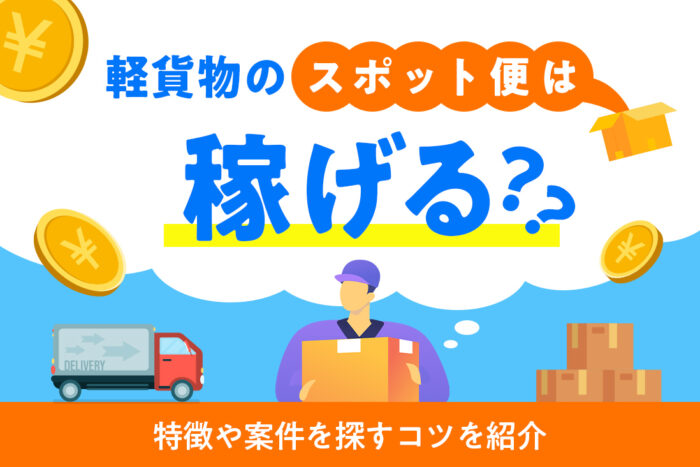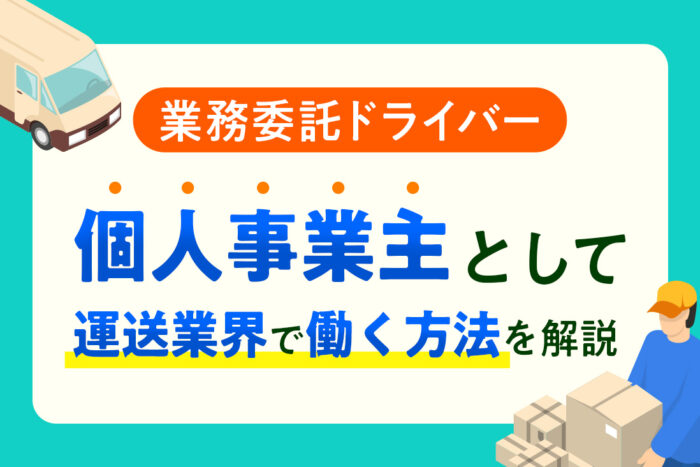運送業の現場では、日々の業務の中で「ヒヤリ」としたり「ハッ」とする場面が少なくありません。そうした出来事を記録・共有するのが「ヒヤリハット報告書」です。報告書を作成することで、事故の原因を早期に見つけ出し、再発防止や安全意識の向上につなげることができます。
本記事では、ヒヤリハット報告書の目的や書き方、実際の記入例、そして運送現場でよくある事例まで詳しく解説します。
目次
ヒヤリハットとは?

ヒヤリハットとは、「ヒヤッとした」「ハッとした」という瞬間を表す言葉で、重大な事故やトラブルにつながる一歩手前の出来事のことです。一見すると問題が起きていないように見えますが、そのまま放置すれば労働災害などの重大な問題に発展する恐れがあります。
そのため、多くの企業ではヒヤリハット事例を共有・分析し、危険の芽を早期に発見して再発防止や安全対策の強化に役立てています。
「ハインリッヒの法則」から見るヒヤリハットの重要性
ハインリッヒの法則とは、「1件の重大な事故の背後には29件の軽微な事故と300件の無傷害事故(ヒヤリハット)が存在する」とする労働災害の統計的法則です。この法則では、大きな事故は偶然起こるものではなく、日常の小さな不注意や危険な行動が重なった結果として発生するものと考えられています。
ヒヤリハットの段階で原因を見つけ出し、早期に改善を行うことで、深刻な事故やトラブルの発生を防ぐ効果が期待できます。
運送業におけるヒヤリハット報告書の目的

運送業では、日々の業務の中で起こり得る危険をいかに早く察知し、防止につなげるかが安全管理の要となります。
ここでは、運送業におけるヒヤリハット報告書の主な目的を見ていきましょう。
労働災害を未然に防ぐ
ヒヤリハット報告書を作成する最大の目的は、労働災害を未然に防ぐことです。運転手が日々の業務で体験する「ヒヤッ」とした瞬間を記録し、共有することで、事故の原因や危険な状況を早期に把握することができます。
得られた情報をもとに職場全体で改善策を検討し、安全運転の意識を高めることが、重大な事故やケガの発生を防ぐことにつながります。
危険を察知する力を高める
ヒヤリハット報告のもう一つの目的は、危険を察知する力を高めることです。運送業の現場では、わずかな油断や判断の遅れが大きな事故につながるおそれがあります。
ヒヤリハット事例を共有することで、運転手がどのような状況で危険を感じたのかを理解し、似たような場面に直面した際には早めに対応する意識が身につきます。
ヒヤリハット報告書の書き方

ヒヤリハット報告書を作成する際は、「5W1H」を意識して記入することが大切です。5W1Hとは、When(いつ)、Who(だれが)、Where(どこで)、What(何をしたのか)、Why(なぜ起きたのか)、How(どのように対応したか)を指す言葉です。
これらの項目を具体的に記載することで、出来事の背景や原因が明確になり、報告内容を共有した際に他の従業員も状況を正しく理解しやすくなります。
ヒヤリハット報告書を作成する際のポイント
ヒヤリハット報告書を作成するときは、客観的な事実に基づいて記入することが重要です。起きた出来事を正確に伝えたうえで「なぜ起きたのか」という原因を考え、再発を防ぐための具体的な対策を示しましょう。
また、専門用語や難しい表現は避け、誰にでも理解できる言葉でまとめることが大切です。事実を正しく共有し、今後の安全につなげる姿勢が求められます。
運送業でよくあるヒヤリハット事例

運送業の現場では、運転中や倉庫内での作業など、さまざまな場面でヒヤリハットが発生します。
ここでは、運送業でよくあるヒヤリハット事例をシチュエーション別にご紹介します。
市街地でのヒヤリハット
市街地は車や歩行者、自転車などが複雑に行き交うため、ヒヤリハットが起こりやすい場所です。
歩行者が死角から突然現れたり、信号が変わる直前に自転車が飛び出したりするケースが多く見られます。また、発進時に隣の車の陰にいた子どもに気づかず、接触しそうになる事例もあります。
交通量の多い場所では、危険をあらかじめ想定する「かもしれない運転」を心がけ、周囲の動きを予測しながら慎重に走行することが重要といえます。
バッグや右左折時のヒヤリハット
バックや右左折時も、ヒヤリハットが発生しやすい場面です。後方の自転車や歩行者に気づかずバックしてしまったり、右折時に内輪差で巻き込みそうになったりするケースも珍しくありません。
特に夜間や雨天時は視界が悪く、危険の見落としが起こりやすくなります。安全を守るためには、目視確認や一時停止の徹底など、基本動作を確実に行うことが大切です。
倉庫内でのヒヤリハット
ヒヤリハットは、倉庫内での作業中にも多く発生します。代表的な事例として、パレット(荷物を載せて運ぶための台)が傾いて崩れそうになったり、フォークリフトと通路で鉢合わせしたり、濡れた床で滑りそうになったりするケースが挙げられます。
倉庫ではドライバーと作業員が同じ空間で作業するため、確認不足や連携ミスが事故につながる恐れがあります。構内ルールの徹底や声かけ・誘導の習慣化が、事故防止には欠かせないといえるでしょう。
運送業におけるヒヤリハット報告書の記入例
運送業の現場で起こり得るヒヤリハットの一例と、報告書の記入例をご紹介します。
【日時】2025年〇月✕日 10:30
【場所】市道沿いのコンビニ駐車場付近
【状況】左側の店舗に入ろうと減速した際、後方から来たバイクが追い越しをかけてきて接触しそうになった。ミラーで確認し、急ブレーキで回避した。
【原因】左折前の後方確認が不十分だった。バイク側も車の動きを予測できていなかった。
【対策】左折時はミラーと目視で後方を二重確認し、合図を早めに出す。また、追い越しの可能性を常に想定して走行する。
ヒヤリハット報告書を作成するときは、感情的な表現を避け、起きた事実を客観的に記載することが大切です。原因や対策を具体的に書くことで、ほかの従業員にも注意を促すことができ、職場全体の安全意識向上につながります。
運送業を安全に続けるにはヒヤリハット報告書の活用が大切
運送業では、日常の小さな「ヒヤリハット」を見逃さずに記録・共有することが、安全を守る第一歩となります。ヒヤリハット報告書は、事故の芽を早期に発見し、再発防止や安全対策につなげるための重要なツールです。
日々の業務で感じた危険を正確に記録し、皆で共有することで、職場全体の危険予知能力が向上し重大な事故を未然に防ぐことができます。安全に運送業を続けるためにも、ヒヤリハット報告書を積極的に活用しましょう。
この記事の執筆者

軽カモツネット編集部
軽カモツネットは株式会社ギオンデリバリーサービスが運営する、軽貨物ドライバー向けの情報発信メディアです。運営元のギオンデリバリーサービスは2013年の設立以来、神奈川県相模原市を中心に業務委託ドライバーの開業支援や宅配サービスの運営など多岐にわたるサポートを行ってきました。拠点数は全国40カ所以上、約2,000名のドライバーが、日々安全で効率的な配送をご提供しています。軽カモツネットでは、軽貨物ドライバーの皆様のニーズに応え信頼される情報を発信してまいります。