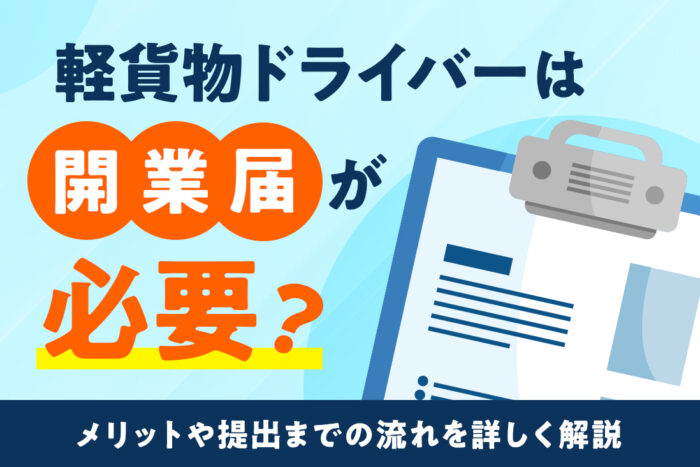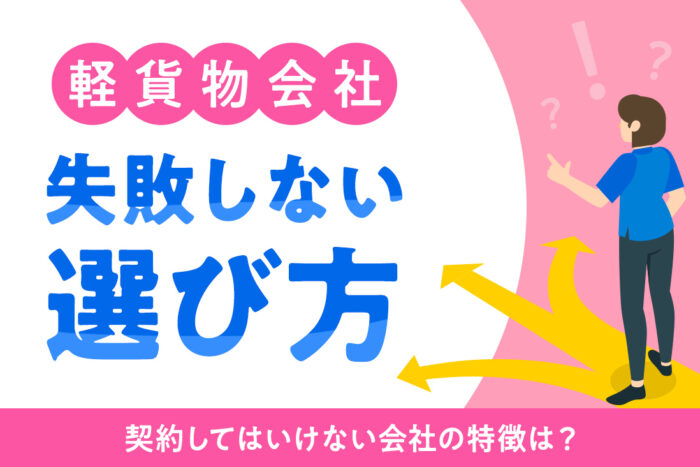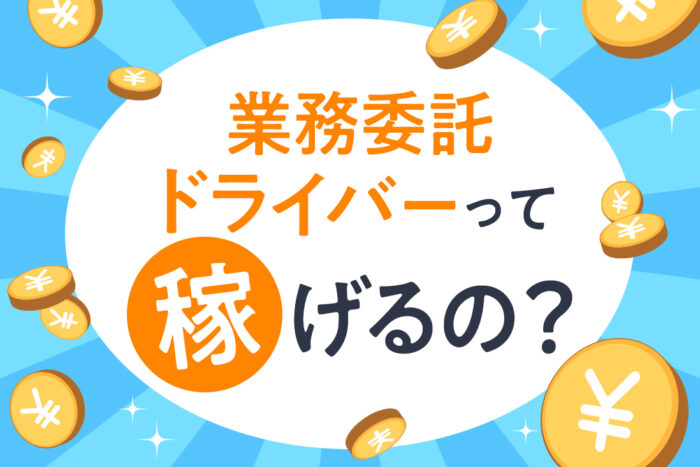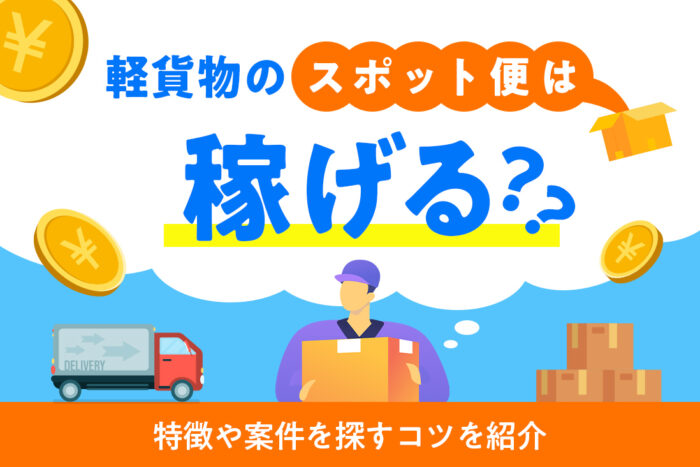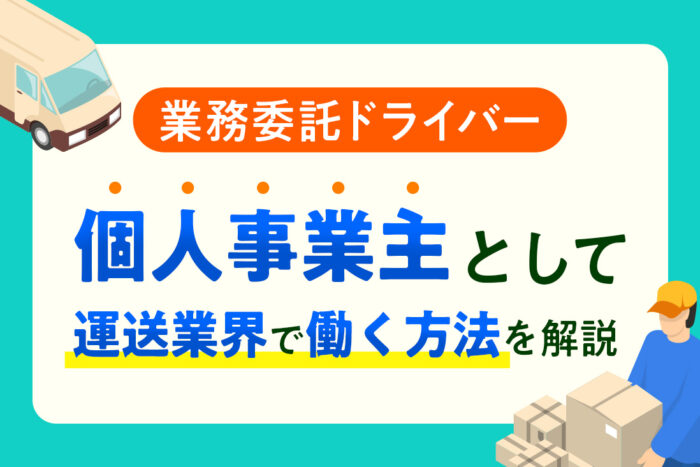社内便とは、企業の本社や支店、営業所など、同一の組織内で書類や荷物をやり取りするための配送手段です。宅配便のように外部へ配送するのではなく、社内の物流を効率化することが目的とされています。
本記事では、社内便の具体的な仕事内容やメリット・デメリットに加え、軽貨物ドライバーとして社内便を始めるためのステップもわかりやすく解説します。
社内便とは?

社内便とは、企業や団体の本社・支店・営業所など、同一組織内で書類や物品をやり取りするための配送手段です。外部への発送ではなく、社内間の連絡・業務連携を目的として定期的に運行されます。
契約書や稟議書、重要資料など、電子化できない原本を安全に届ける手段として利用されるほか、決まったルートと時間で巡回するため、業務の効率化やセキュリティ確保にも役立つ仕組みです。
社内便の仕事内容とは?

社内便の仕事は、企業の拠点間をつなぐ重要な役割を担っています。一般的な宅配とは異なり、扱う荷物やエリア、運行頻度は企業の業務内容によって大きく変わります。
ここでは、社内便の主な仕事内容についてご紹介します。
主な配送内容
社内便で運ぶ荷物は、企業活動に欠かせない重要なものが中心です。たとえば、経理関連の内部書類や契約書、企業戦略に関する資料、製品の試作品などが挙げられます。いずれも外部に漏らせない機密性の高い情報や物品であるため、確実に届けるためのセキュリティ管理が欠かせません。
荷物は軽量かつ小型のものが多く、軽貨物車両での配送に適しています。体力だけでなく、慎重さと正確さが求められる仕事といえるでしょう。
配送エリアと頻度
社内便の配送エリアは、同一ビル内での資料受け渡しから、市内・県内の拠点間、さらには遠方の事業所まで、企業の拠点構成によってさまざまです。
近距離では1日数回の巡回を行うケースもありますが、遠隔地では週数回や指定日のみ運行するなど、企業の規模や配送量により頻度は大きく異なります。
拠点数が多い企業では外部業者に委託する場合も多く、コストや業務内容に合わせて柔軟に設定されています。
社内便と宅配便の違いとは?
社内便は、同一企業内の拠点間で書類や備品をやり取りするための配送手段です。決まったルートを定期的に巡回するのが特徴で、情報漏洩のリスクが低く、社内の物流を効率化できる点が強みです。
一方、宅配便は企業や個人からの依頼を受けて荷物を全国へ届けるサービスを指します。つまり、社内便は「社内専用の物流」、宅配便は「外部向けの配送」という違いがあるといえます。
社内便を請け負うメリット

社内便の仕事には、他の配送業務にはないさまざまな魅力があります。
ここでは、社内便を請け負うことで得られる主なメリットについて詳しく紹介します。
時間の管理がしやすい
社内便の配送は、決められたルートと時間に沿って運行するため、スケジュール管理がしやすいのが特徴です。宅配便のように再配達や急な依頼が発生することが少なく、1日の流れを安定して組み立てることができます。
稼働時間に大きなブレがなく、プライベートと両立しやすい点も魅力です。社内便は、計画的に働きたい人に適した働き方といえます。
ストレスが少ない
社内便の仕事は関係者とのやり取りが中心で、外部のお客様対応やクレーム対応がほとんどありません。そのため、コミュニケーションによるストレスが少なく、落ち着いた環境で業務に集中できます。
人間関係のトラブルやプレッシャーの多い環境が苦手な人にとっても、社内便は続けやすい仕事といえるでしょう。
収入が安定しやすい
長期的に安定した収入を得やすいのも、社内便のメリットのひとつです。企業との契約に基づいて配送を行うため、宅配のように日々の荷物量に収入を左右されにくく、定期的な案件として継続的に仕事を請け負うことができます。
社内便のデメリット
社内便の仕事には多くの魅力がありますが、その一方で注意すべき点も存在します。
ここでは、社内便を請け負う際に知っておきたい主なデメリットを紹介します。
単価が安い
社内便の仕事は安定している反面、1件あたりの単価が比較的低い傾向があります。小型で軽量な荷物が多く、再配達もないため、高単価の宅配案件に比べると報酬水準は控えめです。
また、ルートが決まっている配送が中心となるため、作業の効率化による追加収入の伸びが期待しにくい点もデメリットといえるでしょう。
柔軟性が求められる
社内便は基本的に決まったルートを巡回しますが、企業の事情によって運行スケジュールや配送内容が変更になることもあります。突発的な会議資料の追加や、拠点間の集荷時間の調整など、柔軟な対応が求められる場面も少なくありません。
さらに、企業ごとにルールやセキュリティ手順が異なるため、それらを正確に理解し、臨機応変に行動する必要があります。そうした対応が苦手な方にとっては、負担の大きい仕事といえます。
競合が多い
社内便の仕事は、安定した収入と働きやすさから人気が高く、軽貨物ドライバーの中でも競争が激しい分野です。特に都市部では競合が多いため、未経験者がすぐに参入するのは難しいケースもあります。
長期契約で埋まっている案件も多く、新規で仕事を受けるには根気やタイミングが重要です。安定性が魅力な一方、仕事を得るまでのハードルはやや高めといえるでしょう。
社内便の始め方

社内便の仕事を始める際には、いくつかのステップを踏む必要があります。初心者でも、流れを理解しておくことで、仕事をスムーズにスタートできます。
ここでは、社内便を請け負うために必要な準備と手順を3つのステップに分けて紹介します。
1.車両を用意する
社内便の仕事を始めるには、まず配送に使用する軽貨物車両を準備する必要があります。一般的には、荷室の広さや燃費の良さから軽バンタイプが多く使われています。
車両を準備したら「黒ナンバー(貨物軽自動車運送事業)」の届出を行い、営業用として登録しましょう。自家用車のままでは業務委託を受けられないため、開業前に手続きをしっかり済ませておくことが大切です。
2.委託会社やマッチングサービスに登録する
車両の用意や必要な手続きを済ませたら、次に委託会社やマッチングサービスへ登録して案件を探します。大手企業の下請け案件のほか、フリーランス向けのマッチングアプリを利用して社内便の仕事を見つけることも可能です。
なお、登録の際は、車検証や黒ナンバーの情報、身分証の提出などを求められる場合があります。
3.社内便案件を探す
社内便案件は「ルート配送」や「企業便」といった名称で募集されていることも多いため、案件を探す際には仕事内容をよく確認しましょう。
また、委託会社やマッチングサービスのほか、地元の企業や物流会社に直接問い合わせる方法も有効です。経験や信頼を積み重ねることで、定期契約など安定した案件を紹介してもらえるチャンスが広がります。
社内便は安定性と働きやすさが魅力の配送スタイル
社内便は、安定したスケジュールと働きやすい環境が魅力の配送スタイルです。再配達や顧客対応が少なく、企業間の拠点を巡回するシンプルな業務内容のため、ストレスフリーの環境で計画的に働きたい人に向いています。
宅配便に比べて報酬はやや低めですが、その分、長期契約によって安定した収入を得やすいのがメリットです。慎重さと責任感を持って取り組めば、軽貨物ドライバーとして長く続けられる仕事といえるでしょう。
この記事の執筆者

軽カモツネット編集部
軽カモツネットは株式会社ギオンデリバリーサービスが運営する、軽貨物ドライバー向けの情報発信メディアです。運営元のギオンデリバリーサービスは2013年の設立以来、神奈川県相模原市を中心に業務委託ドライバーの開業支援や宅配サービスの運営など多岐にわたるサポートを行ってきました。拠点数は全国40カ所以上、約2,000名のドライバーが、日々安全で効率的な配送をご提供しています。軽カモツネットでは、軽貨物ドライバーの皆様のニーズに応え信頼される情報を発信してまいります。