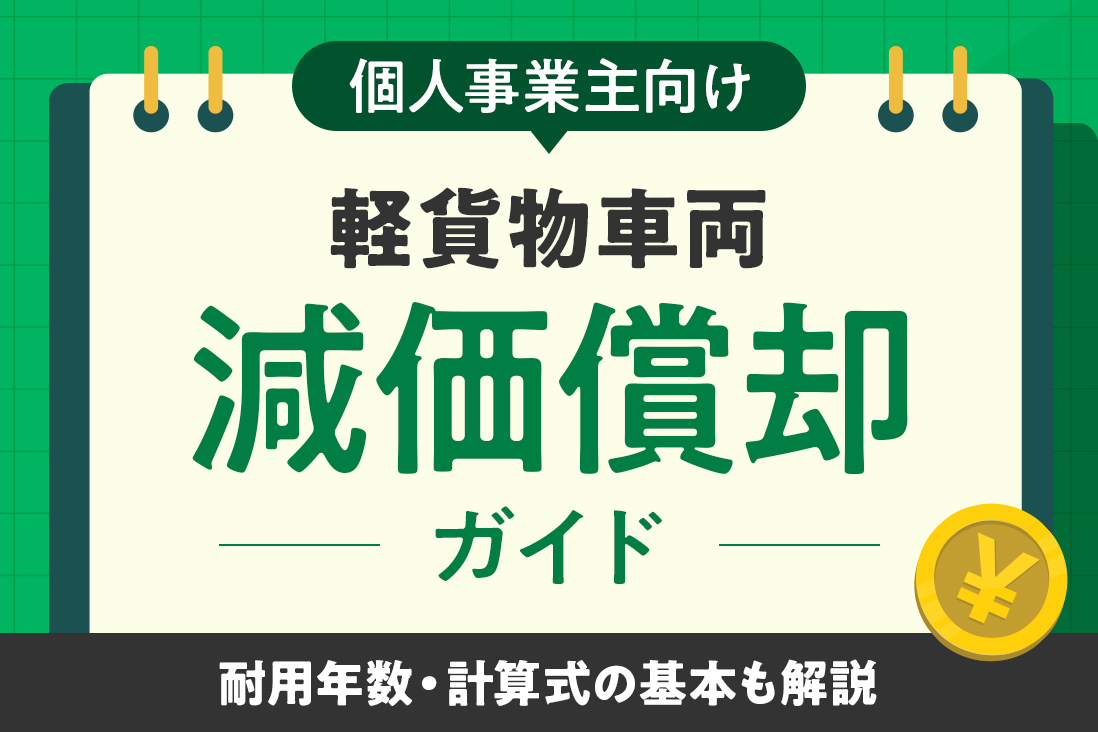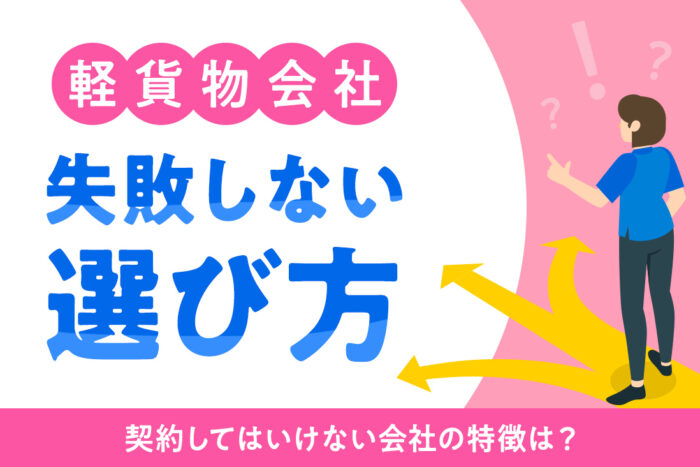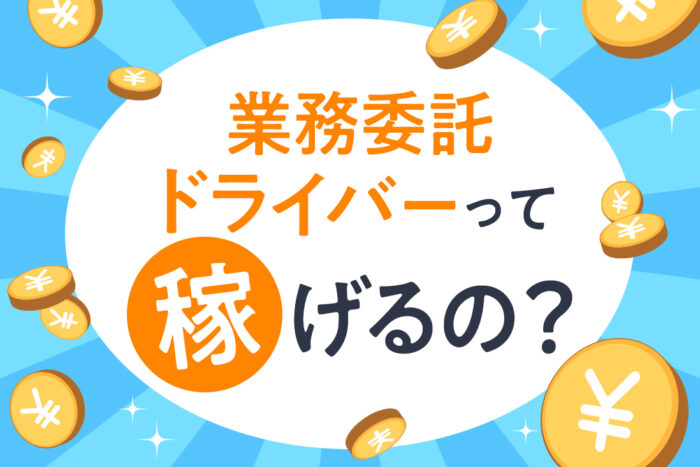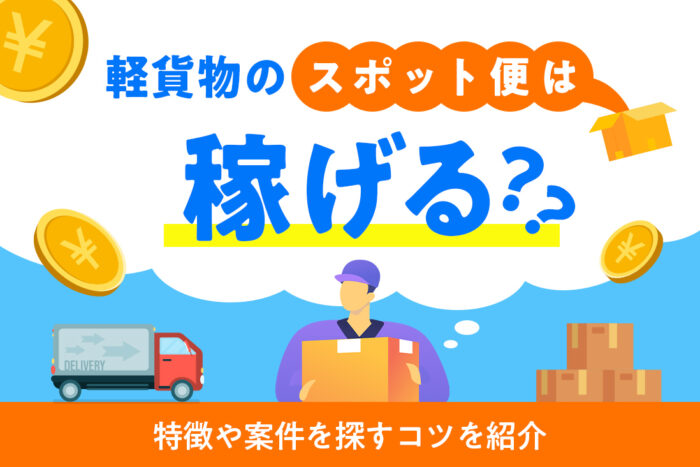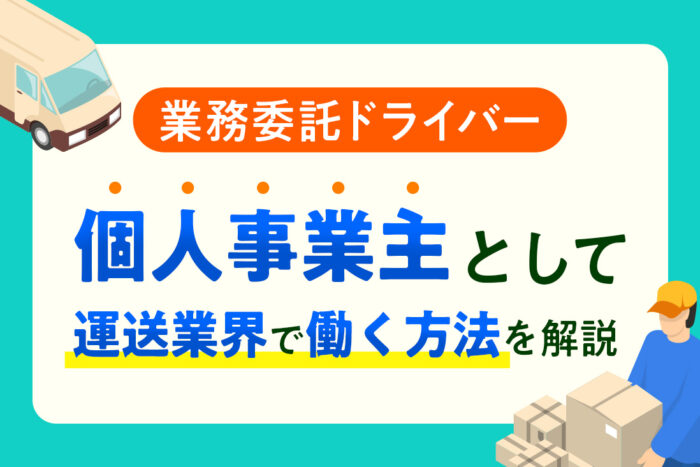個人事業主の軽貨物ドライバーが事業に利用する車両は、適切に経費計上することで税金対策に繋げることができます。しかし、車両の購入費用をその年に全額経費として計上することは原則できず、減価償却により数年に分けて費用化しなければなりません。
本記事では、耐用年数の考え方や計算式といった軽貨物車両の減価償却に関する基本的な知識をわかりやすく解説します。フリーランスのドライバーが知っておくべき、節税効果を高めるための注意点もまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
全国2,000人のドライバーがギオンで活躍しています!
軽貨物配送・業務委託ドライバーの求人応募はギオンデリバリーサービスにお任せください。
・大手ECとのパートナーシップで豊富な案件数
・全国40以上の豊富な物流拠点数
・手厚いガイダンス、安心のサポート環境
未経験者からベテランまで、幅広くドライバーを募集中!ぜひお気軽にご応募ください!
本サイトでは、個人事業主として運送会社と直接契約を結ぶ業務委託ドライバ―の働き方も詳しく紹介しています。全国に40以上の拠点を構え、年齢問わず2,000人ものドライバーに案件を提供しているおすすめの軽貨物会社「ギオンデリバリーサービス」の特徴もまとめていますので、ぜひ下記のリンクからチェックしてみてください。
目次
そもそも減価償却とは?

減価償却とは、事業で使用する高額な資産を購入した際に、その費用を一度に経費として計上するのではなく、使用できる期間(耐用年数)に分けて少しずつ経費化していく会計上の仕組みです。軽貨物車両のように、数年にわたって継続的に使用するものは「固定資産」として扱われ、原則として減価償却の対象となります。
例えば、100万円の軽貨物車を購入した場合、その年に100万円全額を経費にできるわけではありません。国税庁が定める法定耐用年数に基づき、数年間に分けて経費として計上することで、毎年の利益と費用のバランスを適切に保つ必要があります。減価償却を行うことで、実際の事業実態に即した正確な所得計算が可能です。
減価償却は「資産は使うことで少しずつ価値が減っていく」という考え方に基づいています。車両は年数が経つにつれて劣化し、最終的には買い替えが必要になります。その価値の減少分を毎年の経費として反映させるのが、減価償却における本質といえるでしょう。
また、減価償却が必要になるのは、原則として取得価額が10万円以上の資産です。軽貨物車両の場合は多くのケースで減価償却が必要になるといえるでしょう。軽貨物ドライバーとして安定した事業運営を行うためには、減価償却について正しく理解しておくことが大切です。
軽貨物車両に関わる費用は経費計上できる

個人事業主の軽貨物ドライバーが事業で利用する車両は、購入費用だけでなく、維持費も経費として計上することが可能です。具体的な項目としては、以下が挙げられます。
- ガソリン代
- 駐車場代
- 自動車税・重量税
- 自賠責保険料・任意保険料
- 車検費用
- 修理代
- ETC料金
しかし、軽貨物車両を仕事とプライベートの両方で使用する場合、購入費用や維持費の全額を経費にすることはできません。事業で使用した割合に応じて家事按分を行う必要があります。
軽貨物車両の家事按分を行う際には、走行距離や使用日数を基準にするのが一般的です。税務調査で説明を求められる可能性があるため、家事按分を行う場合は走行記録や使用日数といった根拠となるデータをきちんと保存しておきましょう。
以下に、按分比率を求める際の代表的な計算例をご紹介します。
走行距離の割合で按分するケース
年間総走行距離が1,000kmで、そのうち700kmが業務利用だった場合、経費計上できる費用の割合は「700(km)÷1,000(km)×100=70(%)」となります。
使用日数の割合で按分するケース
年間250日車を利用し、そのうち200日が業務利用だった場合、按分比率の計算式は「200(日)÷250(日)×100=80(%)」となり、車関連の出費の80%を経費計上できます。
軽貨物車を経費にする際に知っておくべき注意点

軽貨物車の経費計上を適切に行う際の注意点として、以下の3点が挙げられます。
- 本人または生計を同一にする親族の名義でなければならない
- 事業使用の証明が求められる
- 複数台を計上する際は使用実態を記録しておく
経費として認められるためには、出費が「業務に関連するもの」であることの証明が必須です。特に、家事按分を行う場合は、走行距離や使用日数を記録した帳簿やデータなどを保存し、客観的に説明できるようにしておかなければなりません。
経費計上する軽貨物車両の台数には、明確な上限はありません。しかし、個人事業主が事業用として複数台(特に3台以上)の車を所有するケースは稀であり、税務署から不審に思われる可能性があります。
全ての車が業務で使用されていることを客観的に証明できるように、業務日報といった使用実態の記録をしっかりと準備しておくことが重要です。事業規模や収益に見合わない台数の車両を経費計上していると、税務調査の対象となるリスクが高まります。
軽貨物車両の減価償却の考え方
減価償却とは、何年も使用する高額な固定資産について、使用できる期間(耐用年数)の間で購入代金を分割して経費計上していく方法です。
個人事業主の軽貨物ドライバーが業務で使用する車両も、「高額な固定資産」とみなされます。購入した年に全額を経費計上することは原則できず、減価償却の対象となります。
減価償却の対象となるのは、その資産を取得するためにかかった金額である「取得価額」です。軽貨物車の場合、以下の費用が含まれます。
- 車両の本体価格
- 車両付属品(カーナビ・ETC車載器・アルミホイールなど)
- 納車費用
一方で、自動車税や自動車重量税、各種保険料などは取得価額には含まれず、それぞれ別途経費として計上します。
耐用年数と減価償却費の計算式

減価償却を行うには、まず軽貨物車の法定耐用年数を把握する必要があります。法定耐用年数とは、固定資産に対して法律で定められた使用期間のことです。
国税庁の定める耐用年数表によると、新車の軽自動車(総排気量0.66L以下のもの)の法定耐用年数は4年とされています。
中古の軽貨物車両を購入した場合、中古車は新車よりも既に消耗しているという考え方に基づき、耐用年数が短く設定されます。より短期間で減価償却を進めることができ、節税効果を実感しやすいのはメリットだと言えるでしょう。
中古の軽貨物車両の耐用年数は、新車登録からの経過年数を踏まえて以下のように算出されます。
新車登録から4年未満の車両を購入する場合
「残りの耐用年数+(経過年数×0.2)」という計算式で算出します。新車登録から1年経過した中古の軽貨物車両を購入する場合、残りの耐用年数は3年であるため、「3(年)+(1(年)×0.2)=3.2(年)」となります。
1年未満の端数は切り捨てるため、このケースでの耐用年数は3年です。
新車登録から4年以上経過した車を購入した場合
既に法定耐用年数を経過した中古資産の耐用年数は、「法定耐用年数×0.2」で計算できますが、計算結果が2年未満になる場合は2年とみなされます。
軽貨物車両での計算結果は「4(年)×0.2=0.8(年)」。つまり、法定耐用年数を過ぎた軽貨物車両の耐用年数は一律で2年ということになります。
軽貨物車両の減価償却は定額法で計算する
減価償却の計算方法には定額法と定率法の2種類がありますが、本章では、個人事業主が原則使用する定額法について詳しく紹介します。
定額法は、資産の購入費用を法定耐用年数で割った同じ金額を減価償却費として1年ごとに計上する方法です。計算が比較的簡単で、毎年の経費額が一定のため、資金計画を立てやすいというメリットがあります。
定額法では、「減価償却費=取得原価×定額法の償却率」という計算式が適用されます。償却率は耐用年数ごとに定められており、法定耐用年数が4年である新車の軽貨物車両の場合、償却率は0.250です。
なお、初年度の経費計上額は、購入した月から決算期末までの期間で月割り計算される点には注意が必要です。例えば、12月決算の個人事業主が7月に車を購入した場合、その年は半年分しか経費計上できません。
【ケース別】軽貨物車両の減価償却に関する注意点

軽貨物車の減価償却を行う際の注意点について、ケース別に紹介していきます。
購入した軽貨物車の取得価額が30万円未満だった場合
取得価額が30万円未満の場合、「少額減価償却資産の特例」が適用され、購入した年に全額を一括で経費計上することができます。ただし、特例を利用するためには、以下を始めとした複数の条件を満たしていなければなりません。
- 青色確定申告の申請書を提出していること
- 年間の取得価額の合計額が300万円以内であること
2025年6月時点で、少額減価償却資産の特例の適用期間は2026年3月31日までとされていますが、今後も延長される可能性があります。
なお、取得価額が10万円未満の場合は、この特例を使わずとも一括で経費にできます。
軽貨物車両をローン購入した場合
ローン購入した場合に毎月支払う利息は、そのまま経費として計上できます。ただし、車両本体価格にあたる月々の返済額の元本部分を再度経費計上してしまうと、二重計上になるため注意が必要です。
軽貨物車両をリースで利用している場合
毎月のリース料を全額経費として計上することができます。勘定科目としては「支払手数料」が用いられることが多いです。
車両はリース会社の所有物であるため、利用者側での減価償却は基本的には不要です。ただ、リース契約の種類によっては減価償却の対象となるケースもあるため、事前に契約内容を確認しておくことをおすすめします。
減価償却を活用して節税効果を高めるポイント

減価償却という仕組みは活用方法次第で、節税効果を高めることも可能です。ここでは、減価償却を活用して節税効果を高めるポイントを紹介します。
中古の軽貨物車両を活用する
減価償却による節税効果を高めたい場合、中古の軽貨物車両を選ぶのは効果的な方法のひとつです。中古車は新車に比べて法定耐用年数が短く設定されるため、短期間で減価償却を進めることができます。その結果、毎年の経費計上額が大きくなり、課税所得を圧縮しやすくなります。
特に、法定耐用年数をすでに経過している中古の軽貨物車両は、耐用年数が一律で2年となるため、購入後2年間でほぼ全額を経費にできる点が大きなメリットです。開業直後で利益が出やすいタイミングや、税負担を抑えたい年には、中古車の活用が節税に直結しやすいといえるでしょう。
購入時期を調整して経費計上のタイミングを考える
軽貨物車両の購入時期を意識することも、節税効果を高める重要なポイントです。減価償却費は、購入した月から決算期末までの月数で月割り計算されるため、購入時期によって初年度に計上できる金額が変わります。
例えば、同じ車両を購入する場合でも、期首に近いタイミングで購入すれば初年度から多くの減価償却費を計上できます。一方で、期末近くに購入すると初年度の経費計上額は少なくなります。利益が大きく出そうな年には、あえて早めに車両を購入することで、所得を抑える効果が期待できます。
家事按分を適切に設定する
軽貨物車両を事業とプライベートの両方で使用している場合は、家事按分の設定次第で節税効果が大きく変わります。事業使用割合が高ければ高いほど、減価償却費や維持費として経費にできる金額も増えるのが理由です。
しかし、無理に事業割合を高く設定すると、税務調査で否認されるリスクが高まります。走行距離や使用日数など、客観的に説明できる基準をもとに按分比率を決め、日々の記録を残しておくことが重要です。適正な家事按分を行うことで、安心して節税効果を得ることができます。
少額減価償却資産の特例を検討する
取得価額が30万円未満の軽貨物車両や付属品については、少額減価償却資産の特例を活用できる可能性があります。この特例を使えば、購入した年に全額を一括で経費計上できるため、短期的な節税効果が非常に高くなります。
しかし、この制度は青色申告を行っていることや、年間300万円までといった条件があります。車両本体だけでなく、カーナビやETC車載器などの付属品が条件を満たすかどうかも含めて、適用できるか検討するとよいでしょう。
減価償却以外の経費と組み合わせて考える
節税を考える際は、減価償却だけに注目するのではなく、ガソリン代や保険料、修理費といった他の車両関連経費と組み合わせて全体を見直すことが大切です。減価償却費は毎年一定額が発生しますが、維持費は使用状況によって変動します。
これらを漏れなく、かつ適切に経費計上することで、節税効果を高められます。特に個人事業主の場合、日々の経費管理がそのまま手取り額に影響するため、車両関連費用全体を意識した経理が重要です。
判断に迷ったら専門家への相談も検討しよう
ここまで、個人事業主の軽貨物ドライバーが車両を経費計上する際の減価償却や家事按分といった考え方について解説してきました。ただし、実際の処理には細かいルールや例外も多く、やや複雑に感じられる方も多いでしょう。
税務に関する知識に自信がないドライバーは特に、無理に自己判断せず、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。適切な経理処理を行うことで、不要なトラブルや税務リスクを避け、安心して本業に集中することができます。
軽貨物車両の減価償却に関するよくある質問

軽貨物車両の減価償却に関するよくある質問に回答します。
Q.軽貨物車両は開業前に購入しても減価償却できますか?
開業前に購入した軽貨物車両であっても、開業後に事業で使用していれば減価償却の対象になります。この場合は、開業時点での時価を取得価額として計上し、そこから減価償却を開始するのが一般的です。購入時の金額をそのまま使えるわけではないため、開業前に車を購入する場合は注意が必要です。
Q.減価償却している途中で車を売却した場合はどうなりますか?
減価償却の途中で軽貨物車両を売却した場合は、帳簿上の未償却残高と売却価格との差額を計算し、利益または損失として処理します。売却価格が帳簿価額より高ければ「譲渡益」、低ければ「譲渡損」となり、所得計算に影響します。減価償却が終わっていなくても、売却時点で精算が必要です。
Q.軽貨物車両を買い替えた場合に古い車の減価償却はどうなりますか?
買い替えたからといって、自動的に減価償却が引き継がれるわけではありません。古い車両は売却・廃車などの処理を行い、その時点で減価償却を終了します。一方で、新しく購入した車両については、改めて取得価額と耐用年数を設定し、減価償却を行います。
Q.青色申告でないと減価償却はできませんか?
減価償却自体は、白色申告でも行うことができます。 しかし、30万円未満の資産を一括で経費計上できる「少額減価償却資産の特例」は、青色申告者のみが利用できる制度です。節税効果を最大化したい場合は、青色申告を選択するメリットが大きいといえるでしょう。
Q.車検費用や修理費も減価償却の対象になりますか?
車検費用や修理費は、原則として減価償却の対象にはなりません。これらは「維持管理費」として、その年の経費に一括で計上するのが一般的です。しかし、車両の価値を大きく高めるような改造や設備追加の場合は、取得価額に含めて減価償却するケースもあります。
Q.軽貨物車両を100%事業用にしていれば家事按分は不要ですか?
事業専用として使用しており、プライベート利用が一切ないことを客観的に説明できる場合は、家事按分を行う必要はありません。しかし、実態として私用が混じっているにもかかわらず100%事業用として処理すると、税務調査で否認される可能性があります。使用実態に即した処理が重要です。
減価償却のルールを押さえて税金対策を万全に
個人事業主の軽貨物ドライバーが車両を経費計上する際には、事業利用の実態を客観的に証明した上で、減価償却や家事按分を行うことが求められます。この記事を参考にしながら、正しいルールに基づいて経費を計上しましょう。
経費を漏れなく計上することは、税務上のトラブルを避けるだけでなく、税負担の軽減にも繋がり、より効率的に収益を上げるために欠かせません。不安な点がある方は、税理士のような専門家に相談することも検討してみてください。
この記事の執筆者

軽カモツネット編集部
軽カモツネットは株式会社ギオンデリバリーサービスが運営する、軽貨物ドライバー向けの情報発信メディアです。運営元のギオンデリバリーサービスは2013年の設立以来、神奈川県相模原市を中心に業務委託ドライバーの開業支援や宅配サービスの運営など多岐にわたるサポートを行ってきました。拠点数は全国40カ所以上、約2,000名のドライバーが、日々安全で効率的な配送をご提供しています。軽カモツネットでは、軽貨物ドライバーの皆様のニーズに応え信頼される情報を発信してまいります。