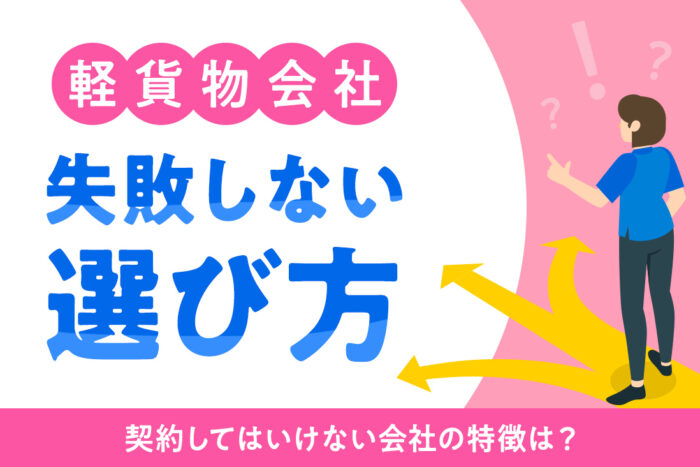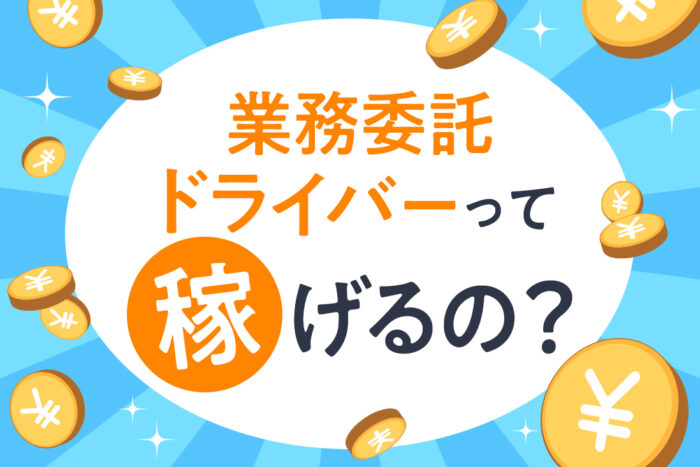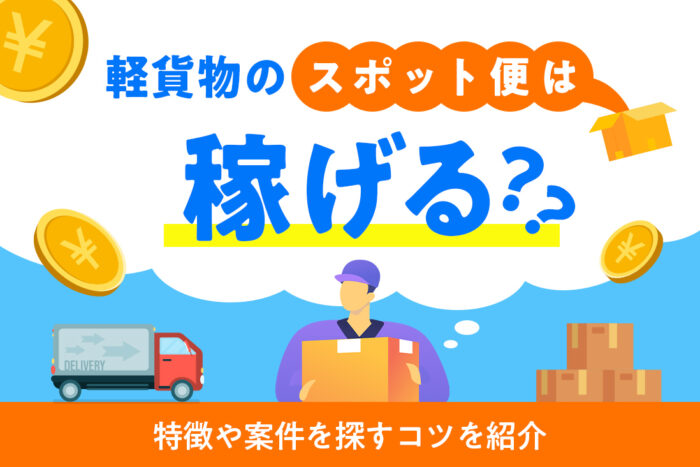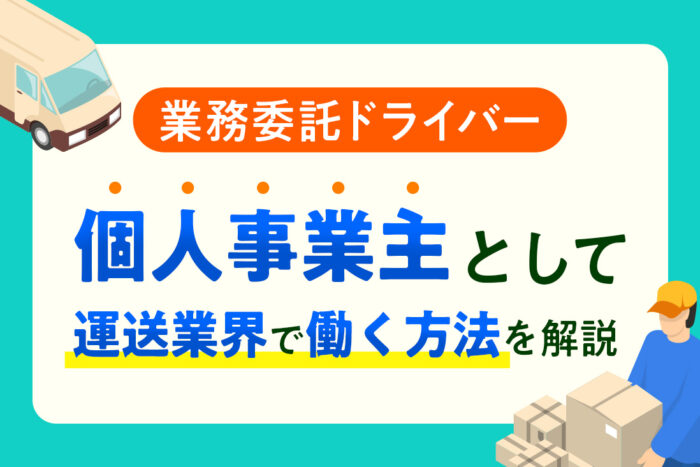私たちが日常的に利用している配送サービスには、「宅急便」と「宅配便」という似たような言葉が存在します。荷物を送ったり受け取ったりする際によく耳にするこれらの用語ですが、実は明確な違いがあることをご存知でしょうか。
配送ドライバーとして働く方はもちろん、荷物を受け取る立場の方も、これらの違いを理解しておくことで、より適切なサービス選択ができるようになります。
今回の記事では、宅急便と宅配便の基本的な違いから、配送業界で使われている様々な用語まで詳しく解説していきます。
目次
「宅急便」と「宅配便」の違いは?

日常の会話やビジネスシーンでは、「宅急便」と「宅配便」を同じ意味で使ってしまうことが少なくありません。しかし、実際のところ両者には明確な違いがあります。ここでは、それぞれの言葉が持つ意味を詳しく解説します。
「宅急便」とは?
「宅急便」とは、ヤマト運輸が1976年に開始した一般消費者向け小荷物配送サービスで、同社が商標登録している独自の名称です。一般的な「宅配便」とは異なり、ヤマト運輸のサービスに限定されます。
通常の宅急便に加えて、冷蔵・冷凍に対応する「クール宅急便」、小型荷物向けの「宅急便コンパクト」など、多彩なラインナップが展開されています。
さらに、「ゴルフ宅急便」や「スキー宅急便」「空港宅急便」など用途別のサービスも用意されており、利用シーンに合わせた柔軟な選択が可能です。
「宅配便」とは?
「宅配便」とは、配送業者が利用者の依頼を受けて、荷物を自宅や指定先まで届けるサービス全般を指す一般的な名称です。日本郵便の「ゆうパック」や佐川急便の「飛脚宅配便」、そしてヤマト運輸の「宅急便」など、各社が提供するサービスの総称として使われます。
つまり、宅急便も宅配便の一種ということになります。日常生活やビジネスの場で広く使われ、どの配送会社を利用する場合でも共通して通じるのが「宅配便」と覚えておくと良いでしょう。
宅配便サービスの種類と特徴

本章では、数多くの配送業者が提供する「宅配便」サービスについて、その種類と特徴に触れていきます。
通常の宅配便サービス
一般的な宅配便サービスでは、以下のような基本的な特徴があります。
- 荷物の3辺(縦・横・高さ)の合計でサイズを決定
- 重量に上限が設けられている
- 配達は手渡しが基本
- 追跡サービスが利用可能
- 破損や紛失に対する補償制度が設けられている
荷物のサイズは縦・横・高さの合計で決定されます。このサイズの上限は配送業者によって異なりますが、三辺合計160cmから200cm程度までの荷物であれば、一般的な宅配便サービスを利用できるケースがほとんどです。重量の上限は25kgから30kg程度である場合が多いですが、これもサービスによって異なります。
特殊な配送サービス
通常の宅配便以外にも、様々な特殊配送サービスが存在します。
クール便は、冷蔵や冷凍が必要な食品類の配送に特化したサービスです。温度管理が重要な商品を安全に届けることができ、生鮮食品の通販などで広く利用されています。
メール便は、小さくて軽い荷物を安価で配送するサービスです。ポストに投函される形で配達されるため、受取人の在宅を必要としない利便性が強みである一方、補償や追跡サービスが制限される場合があります。
配送業界でよく使われる用語の違い
配送業界には、宅急便や宅配便の他にも、混同されやすい用語が多数存在します。ここでは、特に紛らわしい代表的な用語をご紹介します。
発送と配送の使い分け
発送は荷物の送り主が行う行為を指し、荷物を送り出すプロセスの始点となります。例えば、「商品を発送いたしました」という場合、販売者が荷物を配送業者に渡した段階を意味しています。
一方、配送は荷物が送り主から受取人まで届けられる全工程を指します。発送から配達完了まで、荷物が移動する全体的なプロセスを表現する際に使用される用語です。
運送・輸送・配送の関連性
これらの用語は関連性がありながらも、それぞれ異なる意味を持っています。
運送は、主に車両やトラックを使用して荷物を運ぶ行為を指します。配送の一部分として位置づけられ、特定の輸送手段に焦点を当てた表現です。
輸送は、運送や配送を含むより広範囲な概念で、飛行機や船舶なども含めた長距離移動による荷物の運搬を意味します。人の移動も含まれるため、最も包括的な用語となっています。
配送ドライバーが知っておきたい注意点とは?

ここでは、配送ドライバーが宅配業務を担う上で知っておくべき注意点をご紹介します。
「宅急便」と「宅配便」を混同しないようにする
お伝えしているように、宅急便はヤマト運輸の登録商標であり、同社が提供するサービスだけを指します。一方、宅配便には日本郵便や佐川急便など、他社のサービスも含まれます。
両者を混同してしまうと、ヤマト運輸以外のサービスに宅急便という名称を使ってしまい、利用者に誤解を与える恐れがあります。特に問い合わせ対応や伝票の記入時には、正しい用語を使うことを意識しましょう。
各配送業者が提供するサービスの特徴を理解しておくことも重要です。お客様からの質問にスムーズに対応できます。
- 配送可能なサイズや重量の制限
- 時間指定や日付指定の可否
- 特殊な配送オプションの有無
- 補償制度の内容
これらの情報を正確に把握し、必要に応じてお客様に説明できるよう準備しておくことが大切です。
真摯なトラブル対応を心掛ける
配送業務では、様々なトラブルが発生する可能性があります。迅速かつ適切な対応を行うため、以下のポイントを心がけましょう。
- 状況把握と迅速な連絡
- 解決策の提示と会社方針の遵守
トラブル発生時は、まず荷物の破損や遅延などの状況を正確に把握することが重要です。その上で、お客様への連絡は可能な限り迅速に行い、状況を正確かつ丁寧に伝えることが信頼維持につながります。
お客様に解決策を提示する際は、代替案や今後の対応スケジュールを具体的に示し、不安を取り除くよう努めます。この際、雇用主や委託元の運送会社が定める方針やマニュアルに沿った対応を徹底し、独断で安易な約束をしないよう注意しましょう。補償や再配送の手続きについても、事前に確認した上で適切に対応します。
宅急便・宅配便に関するよくある質問

宅急便や宅配便など、配送業界における基本的な用語に関してよくある質問をまとめました。
Q:宅急便と宅配便、どちらを使うのが正しいですか?
ヤマト運輸のサービスを利用する場合は「宅急便」、それ以外の配送業者のサービスを利用する場合は「宅配便」と表現するのが正確です。一般的な会話では「宅配便」を使用すれば、どの業者のサービスでも適用できます。
Q:配送業者によってサービス内容に大きな違いはありますか?
基本的な配送サービスに大きな差はありませんが、料金体系や配送オプション、配送エリアなどに違いがあります。利用目的に応じて最適な業者を選択することをおすすめします。
Q:メール便と宅配便の使い分けはどうすればよいですか?
小さくて軽い荷物で、補償が不要な場合はメール便が経済的です。重要な書類や壊れやすい物、追跡や補償が必要な荷物は宅配便を選択しましょう。
Q:配送料金を安く抑える方法はありますか?
荷物のサイズや重量を適切に調整し、配送距離やサービス内容を検討することで料金を抑えることができます。また、複数の業者の料金を比較検討することも有効です。
「宅急便」と「宅配便」の違いを正しく使い分けよう
「宅急便」と「宅配便」は似ているようで意味が異なる言葉です。両者の違いを理解していないと利用者やドライバーの間で誤解が生じ、手続きに時間がかかる原因になります。
利用者は「宅急便=ヤマト運輸」と覚えておき、状況に応じて各サービスの正式名称を使い分けることが大切です。また、配送ドライバーにとっても各社の特徴を正しく理解することは信頼の確保につながります。
基本的な知識を押さえておくことで、荷物の発送や受け取りを快適に行うことができます。宅急便と宅配便の違いを正しく理解して、上手に使い分けましょう。
この記事の執筆者

軽カモツネット編集部
軽カモツネットは株式会社ギオンデリバリーサービスが運営する、軽貨物ドライバー向けの情報発信メディアです。運営元のギオンデリバリーサービスは2013年の設立以来、神奈川県相模原市を中心に業務委託ドライバーの開業支援や宅配サービスの運営など多岐にわたるサポートを行ってきました。拠点数は全国40カ所以上、約2,000名のドライバーが、日々安全で効率的な配送をご提供しています。軽カモツネットでは、軽貨物ドライバーの皆様のニーズに応え信頼される情報を発信してまいります。