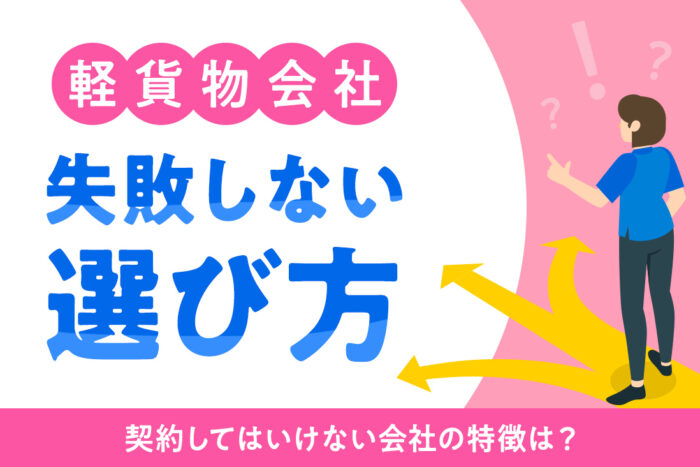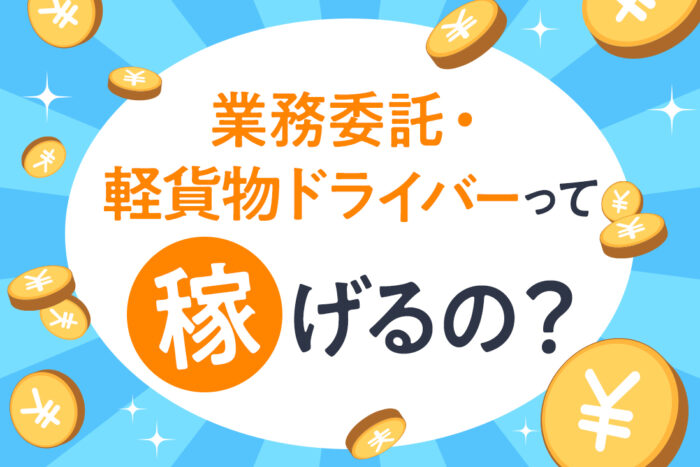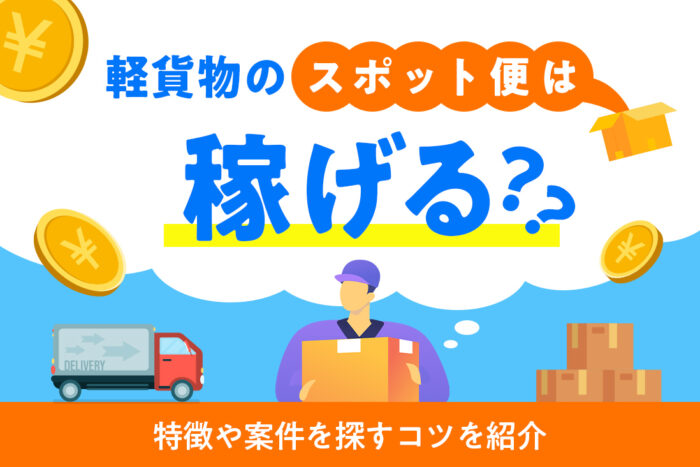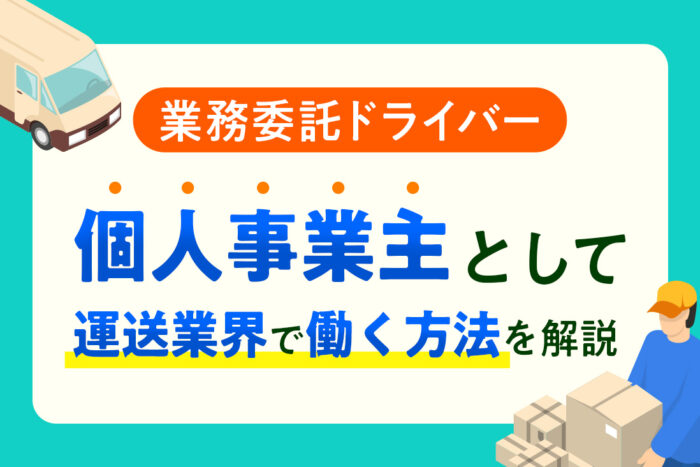EC市場の拡大や深刻な人手不足を背景に、物流業界ではAIを活用した業務効率化が急速に進んでいます。配送業務の最適化、自動化、そして省人化を実現するAI技術は、今後物流現場に欠かせない存在となっていくでしょう。
本記事では、物流業界におけるAI活用の最新事例について紹介していきます。個人事業主として活動する軽貨物ドライバーへの影響にも触れていますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
物流業界が直面する深刻な課題

物流業界は現在、様々な構造的課題に直面しています。こうした課題を理解することは、AI導入の必要性を把握する上で重要です。
配送業務の担い手不足・高齢化
全日本トラック協会の統計によると、道路貨物運送業の運転従事者数は2000年から2015年の15年間で約21.3万人減少。さらに、2015年から2030年の15年間で約24.8万人の減少が見込まれています。
加えて、配送ドライバーの平均年齢は年々上昇し、40〜50代が約半数を占めると言われている一方で、若年層の比率は低い状況が続いています。
長時間稼働と過酷な稼働環境
2024年4月から働き方改革関連法により時間外労働の上限が年960時間に制限され、長時間稼働が常態化していた運送業界に大きな影響が出ています。
慢性的な人手不足がさらに顕著になり、規制の対象外となる個人事業主ドライバーに関しては、逆に長時間稼働がより一層深刻な問題となる可能性も指摘されています。
一方で、荷待ち・荷役・渋滞・再配達対応といった配送ドライバーの実質的な拘束時間は依然として長く、法的な稼働時間短縮とのギャップが生じているのが現状です。
ドライバーの睡眠不足や疲労の蓄積、腰痛、メンタル不調といった健康面のリスクが増大し、安全な業務の遂行に支障をきたすリスクが指摘されています。
配送コストの増加
燃料価格の高騰も、物流業界を圧迫する大きな要因です。ガソリン価格の上昇は、2023年夏頃から社会的な話題となりました。現在は一時に比べると落ち着きを見せているものの、2025年に入っても値上げの報道が続くなど、依然として高止まりの状況が続いています。
燃料費を自ら負担する個人事業主ドライバーにとっては特に、ガソリン代の上昇は収入の減少に直結する深刻な問題となっています。
再配達問題
EC市場の拡大により宅配便の取扱個数は増加の一途をたどっており、全体の約2割が再配達となっているのも、大きな課題の1つです。
再配達の約4割は「配達されることを知らなかった」という理由で発生しているとされており、ドライバーの負担増加と配送効率の低下を招いています。
AI導入がもたらす物流業務の変革
お伝えしたような課題を解決する有効な手段として、AI技術が大きな注目を集めています。単なる業務の効率化にとどまらず、配送計画や人員配置などを含めた業務プロセス全体の再構築への貢献が期待されています。
AIの大きな強みとして挙げられるのが、機械学習機能を備えており、使用するほどシステムの精度が向上していく点です。例えば、過去の配送実績や渋滞パターン、季節変動などのデータを蓄積・学習することで、より正確な予測や計画が可能になるでしょう。
【分野別】物流業界におけるAI活用事例

ここからは、物流業界におけるAIの具体的な活用事例を紹介していきます。本記事では、特に配送ドライバーが担う業務に焦点を当て、AIがどのように現場の効率化や負担軽減に貢献しているのかを紐解いていきます。
配送
配送業務では、ルート最適化を中心にAIの活用が進んでいます。
AI技術は過去の配送データや交通情報、天候などの膨大なデータを瞬時に分析し、最適な配送計画を立案することができます。人の判断では難しい複雑な条件を同時に考慮しながら、リアルタイムで最適なルートや配車計画を導き出せるのです。
主な活用事例としては、次のようなものが挙げられます。
株式会社オプティマインド|Loogia
株式会社オプティマインドが開発した「Loogia」は、AIの力で高精度な配車計画と配送ルートを自動で作成するクラウドサービスです。配送先の位置情報や車両の積載容量、納品時刻、交通状況などの様々な条件を同時に考慮し、最も効率的なルートを数分で計算します。
タキザキロジスティクス株式会社では、従来4人がかりで手作業により行っていた配送計画作成業務にLoogiaを導入し、50〜60件の配送コースを数分で作成。
配車計画にかかる時間を大幅に削減しただけでなく、誰でも最適な計画を立案できる体制を整え、業務の属人化解消にも成功しています。
参考:Loogia|物流戦略策定から実行まで伴走するパートナー
ヤマト運輸株式会社|ビッグデータ×AIで配送業務量予測システムを導入
ヤマト運輸株式会社では、ビッグデータとAIを活用した配送業務量予測システムを導入しています。事前に蓄積された集荷量、配送量、配送先のデータをAIが分析することで、各倉庫にいつ、どのくらいの商品が届くかを高精度で予測することが可能になりました。
予測された業務量に基づいて適切な人員配置を行うことで、配送生産性の向上(最大20%)および走行距離・CO₂排出量の削減(最大25%)が見込めるとされています。
参考:ビッグデータ・AIを活用した配送業務量予測および適正配車のシステム導入について
佐川急便株式会社|伝票処理の自動化
佐川急便株式会社では、かつて配送伝票の情報をすべて手入力で処理しており、繁忙期には100万枚以上の伝票処理が発生していました。
しかし、AIによる文字認識技術を活用した自動入力システムにより、99.995%という高精度での文字の読み取り・自動入力が可能に。月間約8,400時間の作業時間削減を実現し、貴重な労働力をより生産性の高い業務へ振り分けられるようになっています。
また、入力ミスの防止や作業量のばらつきの軽減にもつながり、業務全体の品質向上に寄与しています。
参考:【佐川急便、SGシステム】佐川急便の配送伝票入力業務を自動化するAIシステムが本稼働
顧客対応
配送業務に付随する顧客対応においても、AI技術の活用が進んでいます。
ヤマト運輸株式会社|AIオペレーターによる電話対応
ヤマト運輸株式会社では、集荷依頼の電話対応にAIオペレーターを導入しています。基本的な集荷依頼はAIが自動で受け付け、特別な対応が必要な場合のみ人間のオペレーターが対応する体制へと移行しました。
待ち時間の短縮によって荷主のストレスが軽減されるとともに、スタッフの業務効率も向上しています。
AI導入が個人事業主ドライバーに与える影響

AI技術の進化と普及は、個人事業主として活動する軽貨物ドライバーにも様々な影響を及ぼしています。
業務効率化による収益機会の拡大
配送ルート最適化システムの普及により、これまでドライバー個人の経験や勘に頼っていたルート設定がAIによって自動化され、より少ない手間で最適なルートの選定が可能に。1日あたりの配送件数を増やすことが容易になっています。
最適ルートの活用によって走行距離が短縮されれば、燃料費などの経費削減にもつながるでしょう。
業務の標準化と新規参入のハードル低下
AI技術によって業務の属人化が解消されると、配送ルートの作成や荷物の積み込み順序の決定など、ドライバー個人の経験と勘に頼らざるを得なかった部分がシステム化されます。
経験の浅いドライバーでも効率的な配送が可能になり、新規参入者でも早期に戦力として活躍できる環境が整いつつあると言えます。
さらに、自動検品システムや荷物管理システムが普及すれば、荷物の取り違えや紛失といったトラブルのリスクも低減するでしょう。信用に直結するミスを防げるAI技術は、個人事業主ドライバーにとって大きな安心材料となってくれる可能性が高いです。
競争環境と求められるスキルの変化
AI技術の普及は、ドライバー間の競争環境にも変化を生み出しています。
以前は、地理に詳しいことや効率的なルートを知っていることが大きな差別化要因となっていました。しかし、AIの支援により誰でも最適なルートで配送できるようになると、こうした知識やノウハウの価値が相対的に低下する可能性があります。
今後はAI技術を使いこなすITリテラシーや顧客とのコミュニケーション能力、トラブル発生時の臨機応変な対応力など、人間ならではのスキルがより重要になると考えられます。
システムが提示するルートを機械的に辿るだけでなく、現場の状況に応じて柔軟に判断できるドライバーが重宝されていくでしょう。
AI導入に伴う初期投資とランニングコストの発生
個人事業主ドライバーがAI技術を活用するためには、一定の初期投資が必要になる場合が多いです。配送ルート最適化アプリやスマートフォン、タブレット端末などを導入する場合、初期費用に加え、月額利用料などのランニングコストが発生します。
ただし、これらの投資により得られる業務効率化やコスト削減の効果は大きく、中長期的には投資額を上回るリターンが期待できるでしょう。システム導入前に費用対効果をしっかりと見極め、自分の業務スタイルに合ったツールを選択することが重要です。
AI活用における課題と導入のポイント
物流業界でAIを効果的に活用するためには、課題を正しく理解し、計画的に対応していくことが重要です。
AIの精度は入力データの質に大きく左右されるため、配送先や車両、道路状況などの情報を正確に収集・管理できる体制を整えることが欠かせません。
また、AIが算出した結果をそのまま活用するのではなく、現場ドライバーの経験や知見を反映させながらPDCAサイクルを回していく姿勢も求められます。
AIを使いこなし、業務フローを継続的に改善していくことで、初めて本質的な業務効率化を実現できるようになるでしょう。
AI活用で切り拓く物流業界の未来
物流業界におけるAI活用は、配送ルートの最適化や顧客対応の効率化など、多方面で進展しています。人手不足や長時間稼働、コスト上昇といった課題を抱える物流業界において、AIは欠かせない存在となっていくでしょう。
軽貨物ドライバーにとっても、AIは業務効率化や収益向上を支援してくれる強力なツールです。今後はAIを使いこなすスキルに加え、柔軟な判断力や顧客対応力といった人間ならではの強みを磨くことが求められます。
AIと人の力を組み合わせ、持続可能な物流システムを築くことが、これからのドライバーに必要な視点と言えるでしょう。
この記事の執筆者

軽カモツネット編集部
軽カモツネットは株式会社ギオンデリバリーサービスが運営する、軽貨物ドライバー向けの情報発信メディアです。運営元のギオンデリバリーサービスは2013年の設立以来、神奈川県相模原市を中心に業務委託ドライバーの開業支援や宅配サービスの運営など多岐にわたるサポートを行ってきました。拠点数は全国40カ所以上、約2,000名のドライバーが、日々安全で効率的な配送をご提供しています。軽カモツネットでは、軽貨物ドライバーの皆様のニーズに応え信頼される情報を発信してまいります。