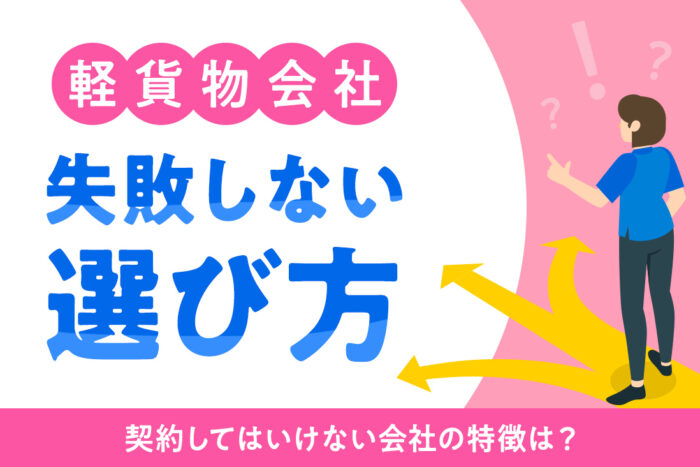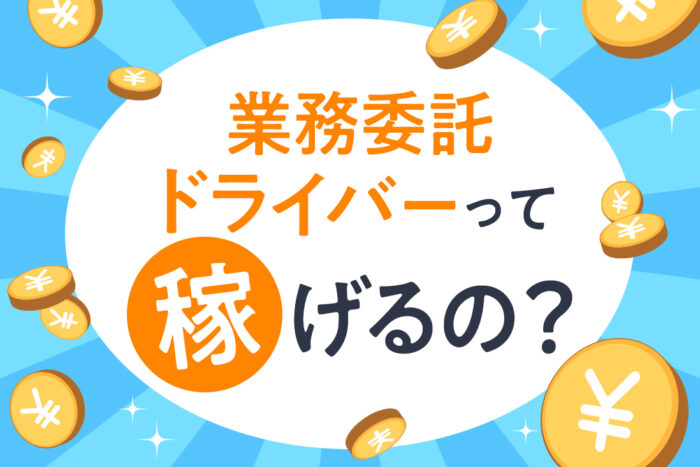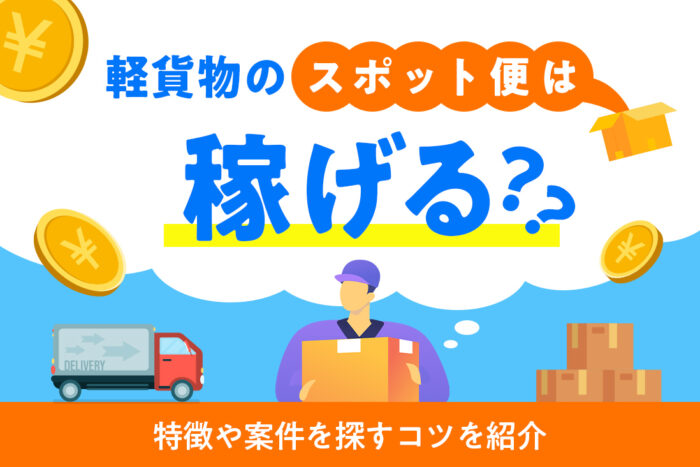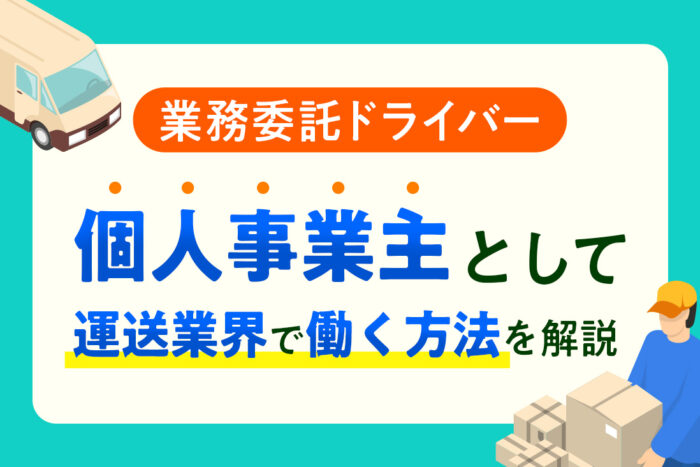今後実施が予定されている高速道路の深夜割引の変更や見直しは、配送ドライバーにとってかなり重要なトピックの1つ。「値上げだ」「一部の運送会社だけが得をする」といった批判の声が相次いでおり、実質的な改悪と捉える声も少なくありません。
本記事では、高速道路深夜割引の変更・見直しが具体的に何をもたらすのか、その詳細をわかりやすく解説します。旧制度と新制度の比較や制度変更の背景にある問題点を深掘りしていきますので、ぜひ参考にしてください。
これまでの深夜割引の仕組み
現在の高速道路の深夜割引制度は、夜間交通の高速道路への転換や、市街地での騒音・渋滞緩和を目的として2004年に導入されました。午前0時から午前4時までの間に高速道路を走行するETC車に、通行料金の3割引が適用されるというものです。
現行の割引制度の問題点とは

現行の制度の大きな特徴は、割引時間帯だけでなく、割引対象時間に高速道路を利用していれば、その前後の時間帯の走行にも割引が適用される点にあります。
午前0時を少しでも過ぎて高速道路を出る、または午前4時の直前に高速道路に乗るなど、うまいタイミングで料金所を通過すれば、通行料金を大幅に安くすることができるのです。
しかし、この”うまいタイミング”を狙うあまり、「0時待ち」と呼ばれる以下のような深刻な社会問題が発生していました。
- サービスエリアや料金所手前での滞留
- ドライバーの労働環境悪化
サービスエリアや料金所手前での滞留
割引の適用が始まる0時直前には、通行料金を安くしたい多くの車、特に配送業務を行う車両がサービスエリアや料金所手前で待機・滞留するようになりました。こうした待機行動により、以下のような問題が引き起こされています。
- サービスエリアが満車になり通路・加速車線・減速車線への停車を余儀なくされる
- 料金所手前で割引待ちの車による長い渋滞ができる
- 二重駐車により車の出入りが妨げられる
なお、二重駐車とは、既に駐車されている車の隣や前に別の車を駐車して、本来の駐車スペースを塞ぐ行為を指します。
上記のようなケースは、交通事故に繋がるリスクが高く非常に危険です。実際、2022年4月には、パーキングエリアの入り口手前付近の路肩に駐車していた大型トラックに別のトラックが追突し、死亡事故につながる痛ましい事例も発生しています。
参考:深夜の高速道路 トラックの列で渋滞 「0時待ち」の謎|NHK事件記者取材note
ドライバーの労働環境悪化
通行料を抑えるため、運送会社がドライバーに対し、0時直後に高速道路を降りる、あるいは4時直前に入るといった割引待ちの待機を指示するケースが散見されます。
その結果、業務終了後に高速道路上で時間を潰したり、早朝に高速道路に出向いたりしなければならず、ドライバーの労働環境の悪化が問題となっています。
こうした状況の深刻化を受け、国が有識者や高速道路会社、大手運送会社関係者を集めて対策を協議し、今回の割引内容の変更に至ったというわけです。
新しい深夜割引の主要な変更点

今回の深夜割引の見直しは、2023年1月に国土交通省と高速道路会社によって発表され、その具体的な運用方法が確定しました。
当初は2025年3月頃からの移行が予定されていましたが、システム整備の遅れにより2025年7月頃へと延期され、同年5月28日には制度導入の再延期が決定しました。正式な開始時期は、2025年6月時点では未定となっています。
新しい深夜割引における5つの重要な変更点について、以下に詳しくまとめています。
割引適用時間帯の拡大と割引対象の見直し
新制度では、割引適用時間がこれまでの午前0時〜午前4時から、午後10時〜翌午前5時へと大幅に拡大されます。さらに、前後の時間帯の走行に対する割引は適用されなくなります。
これにより、旧制度で可能だった、割引適用時間帯に入るまで料金所の手前で待って全区間の割引を受けるといった時間調整は難しくなるでしょう。なお、割引率はこれまでと同じ3割です。
上限距離の設定
前後の時間帯の走行が割引の対象外になると、割引適用時間帯の間にできるだけ距離を稼ごうと、無謀な運転をするドライバーが出現することが懸念されます。そのため、新制度では、割引が適用される距離に対して以下のような上限が設定されました。
- 軽自動車等・普通車・中型車・乗合型自動車:1時間あたり105kmまで
- 大型車・特大車(乗合型自動車を除く):1時間あたり90kmまで
つまり、軽貨物車両の場合、2時間で240km移動しても「105(km)×2(時間)=210(km)」分しか割引されません。スピード超過などを防ぐため、「割引のためにスピードを出しても意味がない」仕組みが採用されています。
割引方法が後日還元型に変更
現行の深夜割引は、高速道路の出口で通行料金から直接差し引かれる形で適用されていました。新制度では、後日還元型による割引制度に変更。ETCマイレージサービスのポイントまたはETCコーポレートカードの還元額として加算されます。
上記の変更により、割引の適用を受けるためにはETCマイレージサービス、またはETCコーポレートカードの事前登録が必須となります。還元されたポイントは高速道路の通行料金にしか使うことができず、現金として利用することはできません。
さらに、ポイントには有効期限があり、付与された年度の翌年度末を過ぎると失効してしまう点にも注意が必要です。
長距離逓減制の拡充
新制度では、400kmを超える長距離走行に対する逓減(ていげん)制が拡充されます。これは高速道路の利用距離が長くなるほど、1kmあたりの通行料金が安くなる仕組みで、長距離運転による通行料金の負担増を軽減することが目的です。
現在と見直し後の割引幅はそれぞれ以下の通り。深夜割引とは異なり、ETC登録の有無に限らず割引を受けることができます。
<現在>
| 100~200km | 25% |
|---|---|
| 200km~ | 30% |
<見直し後>
| 100~200km | 25% |
|---|---|
| 200~400km | 30% |
| 400~600km | 40% |
| 600~800km | 45% |
| 800km~ | 50% |
激変緩和措置(5年程度を予定)の導入
上述の見直しに伴う長距離利用の料金負担増や新たな交通集中を抑制するため、制度運用開始から約5年間、2つの緩和措置が導入されます。
1つ目は「深夜割引適用時間帯を走行し、かつ一連の走行が1,000kmを超えた場合、1,000kmを超えた走行分にも30%の割引率が適用される」というもの。
例えば、午前1時から午後3時の間で1,200km走った場合、午前1時~午前5時(深夜割引適用時間内)の走行分だけでなく、200kmの走行分(1,000kmの超過)も30%引となります。
もう1つは、「午後10時を過ぎて料金所から出た車は、午後10時台に走行した分の通行料金に最大20%の割引率が適用される」というものです。
つまり、午前3時から午後10時45分まで連続して走行した場合、午前3時~午前5時(深夜割引適用時間内)までの走行分に30%、午後10時~午後10時45分(激変緩和措置の適用時間内)までの走行分に最大20%の割引を受けられます。
深夜割引の見直しが「改悪」と指摘される背景

ドライバーの負担を軽減するために導入された高速料金の深夜割引の見直しですが、「改悪」と受け取る方が多いのも事実です。その背景として、以下の2点が挙げられます。
- 長距離運行のコストが増大する
- ドライバーの負担が増大する
長距離運行のコストが増大する
新制度では、割引が適用される上限距離が1時間あたり105kmあるいは90kmに設定されますが、交通状況やルートによっては「短すぎる」と感じられるケースもあるでしょう。実際の走行距離が上限を超えてしまうと、超過分に対する割引は適用されません。
運行コストが増大する可能性があるにも関わらず、それに合わせて配送運賃が値上げされることは考えにくいのが現状です。経費をすべて自己負担する個人事業主のドライバーにとっては特に、経費がかさみ収益の悪化に繋がりかねません。
ドライバーの負担が増大する
割引時間帯が午後10時から午前5時という深夜帯に設定されていることから、ドライバーの稼働時間が夜間に偏り、身体的な負担が増大する可能性が指摘されています。
今回の見直しは「0時待ち」の解消を目的の1つとしていますが、割引の適用が時間帯で区切られる以上、「待つ時間帯がずれるだけだ」といった不満の声も少なくありません。
割引適用時間帯に高速道路上にいれば良かった現行の制度に比べ、実際に稼働していなければならない新制度の方が、ドライバーにとっては不利だという見方が多いです。
今後の動向を注視して効率の良い働き方を
今回の高速道路深夜割引の見直しは、いわゆる「0時待ち」の解消や、ドライバーの過酷な労働環境の改善を目的とした制度変更とされています。しかし、現場の運送会社や配送ドライバーの間で「かえって負担が増えるのでは」と懸念する声も少なくありません。
導入の延期が繰り返されているこの制度ですが、いずれ実施されることを見越し、今後の動向を注視するとともに、割引を最大限に活用できるよう準備を整えておくことが重要です。
個人事業主の軽貨物ドライバーにとっては、運行ルートや時間帯の見直し、必要に応じた荷主との運賃交渉といった対応も視野に入れるべきタイミングかもしれません。制度に振り回されるのではなく、制度に合わせて柔軟に対応していく姿勢が求められていくでしょう。
この記事の執筆者

軽カモツネット編集部
軽カモツネットは株式会社ギオンデリバリーサービスが運営する、軽貨物ドライバー向けの情報発信メディアです。運営元のギオンデリバリーサービスは2013年の設立以来、神奈川県相模原市を中心に業務委託ドライバーの開業支援や宅配サービスの運営など多岐にわたるサポートを行ってきました。拠点数は全国40カ所以上、約2,000名のドライバーが、日々安全で効率的な配送をご提供しています。軽カモツネットでは、軽貨物ドライバーの皆様のニーズに応え信頼される情報を発信してまいります。